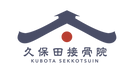
~肩、首、腰の接骨院~
本質と向き合い、健やかな未来を創る
~肩の痛み~
なぜあなたの肩は痛むのか?
肩の専門家が解き明かす「痛みの正体」
肩関節の機能解剖学
「腕が上がらない」「夜中にズキズキ痛む」「何だか肩がゴリゴリする」。 そんなつらい肩の痛みに、多くの方が悩まされています。
実は、肩の関節は体の中で最も自由自在に動く、非常に高性能な部分です。しかしその反面、とてもデリケートで不安定な構造をしています。まるで、小さな台座の上に大きなボールが乗っているようなものです。この絶妙なバランスは、「骨格」「靭帯などの支え」「筋肉のコントロール」という3つのチームが協力し合うことで、奇跡的に保たれています。 あなたの肩の痛みの原因を突き止めるには、まず、この素晴らしいチームの仕組みを知ることが第一歩です。一緒に見ていきましょう。
1.肩の動きを支える「骨格チーム」
私たちが「肩」と呼んでいる部分は、実は4つの関節が連動して動く「複合体」です。どれか一つでも不調になると、スムーズな動きが失われてしまいます。
-
肩甲上腕(けんこうじょうわん)関節 (図2)
-
いわゆる「肩関節」の中心です。「上腕骨」という腕の骨の先端(ボール)が、「肩甲骨」の浅いお皿(関節窩(図1))にはまっています。この”浅いお皿”のおかげで腕をグルグル回せますが、その分、ボールが外れやすく不安定なのです。
-
-
肩鎖(けんさ)関節 & 胸鎖(きょうさ)関節 (図2、3)
-
「鎖骨」を中心とした関節で、腕と体をつなぐ”吊り橋”のような重要な役割を担っています。腕を上げる時、この”吊り橋”がしなやかに動くことで、肩全体の動きをサポートします。
-
-
肩甲胸郭(けんこうきょうかく)関節 (図3)
-
肩甲骨は、肋骨の上を滑るように動きます。これは正式な関節ではありませんが、機能的には非常に重要です。腕を上げる時、腕の骨が「2」動くのに対して、肩甲骨が「1」動くという、見事なチームワーク(肩甲上腕リズム)が存在します。このリズムが崩れると、多くの肩の不調を引き起こします。
-
-
烏口肩峰(うこうけんぽう)アーチ (図4)
-
肩の上部にある、骨と靭帯でできた”屋根”のような部分です。この屋根の下には、筋肉の腱などが通る「肩峰下腔(けんぽうかくう)」というトンネルがあります。肩の動きが悪くなると、このトンネル内で腱がこすれてしまい、痛みの原因となります(インピンジメント症候群)。
-
2.関節を固定する縁の下の力持ち - 「静的安定化機構」
肩がグラグラしないように、筋肉の力を使わずにガッチリと固定している”支え”の役目を持つ組織です。
-
関節包(かんせつほう)(図5) & 関節上腕靭帯(かんせつじょうわんじんたい)(図6)
-
肩甲上腕関節を包む”丈夫な袋”です。この袋の一部は分厚いバンド(靭帯)になっていて、関節を補強しています。特に、腕を振り上げる動作の際には、ハンモックのように下から関節を支える靭帯(下関節上腕靭帯)が、脱臼を防ぐために重要な働きをします。
-
-
関節唇(かんせつしん)(図7)
-
関節のお皿のフチについている、軟骨の”土手”です。この土手が壁の役割をすることで、浅いお皿を深くし、ボールがズレないように安定性を高めています。
-
3.肩を自在に操る司令塔 - 「動的安定化機構」
実際に肩を動かしながら、適切な位置に安定させるという、最も重要な役割を担う筋肉のグループです。
-
腱板(けんばん)- ローテーターカフ
-
肩のインナーマッスル(深層筋)として知られ、棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋という4つの筋肉がまるでボールをつかんでいるかのように上腕骨頭の周りに付着しています(図8)。
-
これらの筋肉は、腕を動かすだけでなく、4つの筋肉が絶妙な力加減で”綱引き”をするように、上腕骨のボール部分をお皿の中心にグッと引きつけ続けます。
-
このおかげで、三角筋(図9)のような大きなアウターマッスルが力強く腕を上げても、関節がズレることなくスムーズに動くことができるのです。多くの肩の痛みは、この腱板の機能低下や損傷が原因となっています。
-
-
肩甲骨の周りの筋肉
-
僧帽筋や前鋸筋(図9)など、肩甲骨を背中の正しい位置に固定したり、腕の動きに合わせて滑らかに動かしたりする筋肉です。
-
猫背などでこれらの筋肉の働きが鈍ると、先述の「肩甲上腕リズム」が崩れ、結果として腱板に負担がかかり、痛みに繋がります。肩の痛みの根本原因が、実は肩甲骨の動きの悪さにあることは少なくありません。
-
-
上腕二頭筋長頭腱(図9)(じょうわんにとうきんちょうとうけん)
-
「力こぶ」の筋肉につながる腱で、関節の中を通り、骨頭が上にズレるのを抑える補助的な役割を担っています。
-
各疾患の解説
私たちの生活に深く関わる「肩の痛み」。ひとくちに肩の痛みと言っても、その原因は様々です。ここでは、代表的な肩の痛みの原因となる疾患について、なぜ痛むのか、そしてどのような治療法があるのかを、最新の科学的根拠を交えながら、分かりやすく解説していきます。
1. 肩関節周囲炎(いわゆる四十肩・五十肩)
どんな症状?どのくらいの人がなるの?
一般的に「四十肩・五十肩」と呼ばれるこの疾患の正式名称は「癒着性肩関節包炎/肩関節周囲炎」といい、その名の通り40代から50代の方に多く見られます¹。主な症状は、肩の痛みと動きの制限です。ある日突然、髪をとかす、服を着替える、背中に手を回すといった何気ない動作で肩に鋭い痛みが走るようになります²。特に、夜中に痛みが強くなる「夜間痛」で目が覚めてしまうことも多く、生活の質を大きく下げる原因となります²。
なぜ痛くなるの?
肩関節を袋のように包んでいる「関節包」という組織が、加齢などが原因で炎症を起こすことから始まります¹。炎症が続くと、線維芽細胞という細胞が活発になり、関節包が分厚く硬くなってしまいます。そして周囲の組織とくっついて(癒着して)しまうのです¹。この状態が、肩の動きを著しく悪くする「拘縮(こうしゅく)」です。このため、自分で動かそうとしても、他の人に動かしてもらおうとしても、ある範囲以上には腕が上がらなくなります²。 この疾患は、大きく3つの時期に分けて進行するのが特徴です³。
-
疼痛期/炎症期(Freezing Stage): 痛みが最も強く、夜も眠れないほどです。炎症が活発で、徐々に肩の動きが悪くなっていきます³。
-
拘縮期/凍結期(Frozen Stage): 激しい痛みは少し和らぎますが、肩が凍ったように固まり、動きが最も制限される時期です³。
-
回復期/解凍期(Thawing Stage): 痛みはほとんどなくなり、固まった肩がゆっくりと時間をかけて溶けていくように、少しずつ動きが戻ってきます³。
どんな治療法があるの?
治療は、これらの病期に合わせて行うことが非常に重要です。炎症期には、まず炎症を抑えるために安静を保ち、痛みが強い場合は病院にてお薬(非ステロイド性抗炎症薬)やステロイド注射を行うこともあります⁴。無理に動かすと、かえって炎症を悪化させてしまうことがあります。痛みが落ち着き、拘縮期に入ったら、硬くなった関節包を根気強く伸ばしていくための運動療法が施術の中心となります⁴。
エコーで何がわかるの?
柔道整復師は診断を行いませんが、エコーを用いて体の内部を「観察」することで、より安全で的確な判断を行うことができます。当院では、エコーを用いて肩の中の状態を詳しく観察します。エコーを使うと、炎症(図10)が起きている場所や関節包の厚さ、筋肉や腱の状態をリアルタイムで観察することができます¹⁰。これにより、現在の肩がどの病期にあるのかを正確に判断し、最適な施術方針を立てるのに役立ちます。
ラジオ波『深層筋温熱療法』でどう良くなるの?
『深層筋温熱療法』は、体の表面を温めるホットパックなどとは全く異なり、高周波のエネルギーを使って体の奥深く、痛みの原因となっている部分に直接熱を発生させる先進的な治療法です¹¹。
-
拘縮期に真価を発揮 拘縮期に硬く厚くなってしまった関節包は、『深層筋温熱療法』の得意なターゲットです。RETモードという特殊な方法で、電気抵抗が高くなっている硬い関節包を選択的に温めることができます¹²。コラーゲン線維でできた関節包は、温められるとその柔軟性が増し、伸びやすい状態になります¹²。この「温めてから動かす」アプローチにより、施術の効果を最大限に引き出すことができます。硬いゴムを温めると柔らかくなるのをイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。実際、標準的な施術に『深層筋温熱療法』を追加した群は、そうでない群に比べて痛みと機能が有意に改善したという質の高い研究報告があります⁵, ⁶。
-
疼痛期・炎症期の痛みにもアプローチ 痛みが強い炎症期には、温めることが逆効果になる場合があります。しかし、ラジオ波治療器には出力を調整して熱を発生させない「非熱モード」があります¹²。このモードでは、高周波の電磁波が持つ生物学的刺激作用により、細胞レベルで炎症を抑え、痛みを和らげる効果が期待できます¹²。
『深層筋温熱療法』は、このように病期に応じた使い分けが可能であり、運動療法と組み合わせることで、つらい五十肩の回復を力強くサポートします⁵。
2. 肩こりと自律神経失調症
どんな症状?
「肩こり」は正式な病名ではありませんが、首すじから肩、背中にかけての重だるさ、痛み、張り感などを総称した言葉です。これがひどくなると、頭痛や吐き気、めまい、腕のしびれなどを伴うこともあります。こうしたつらい症状が続くと、気力が湧かず、集中力が低下するなど、精神的な不調につながることも少なくありません。
なぜ痛くなるの?
肩こりの主な原因は、長時間同じ姿勢でいること(デスクワークやスマホ操作など)、運動不足、ストレスなどです。これらの要因が重なると、肩周りの筋肉が常に緊張した状態になり、硬くこわばってしまいます。筋肉が硬くなると、内部の血管が圧迫されて血行が悪くなります。血行不良に陥った筋肉には、酸素や栄養が十分に行き渡らず、代わりに乳酸などの疲労物質が溜まっていきます。この「筋肉の緊張 → 血行不良 → 疲労物質の蓄積」という悪循環が、「こり」や痛みの正体です。
また、肩こりは自律神経の乱れと深く関係しています。ストレスなどによって、体を興奮・緊張させる「交感神経」が過剰に働くと、血管が収縮して血行が悪くなり、筋肉が緊張しやすくなります。逆に、体をリラックスさせる「副交感神経」がうまく働かないと、心身の緊張が解けず、肩こりが慢性化しやすくなります。
どんな治療法があるの?
一般的には、マッサージや指圧といった手技療法、鍼灸治療、ストレッチ、姿勢の改善指導などが行われます。これらは硬くなった筋肉をほぐし、血行を促進することを目的としています。
エコー(超音波)で何がわかるの?
エコーでは、筋肉がどのくらい硬くなっているか(筋硬度)、血流がどのくらい滞っているか(血流動態)を客観的に評価することが可能です。また、肩こりだと思っていた症状が、実は次に紹介する腱板損傷など、他の疾患が原因である可能性もあります。エコーで内部構造を詳しく見ることで、そのような隠れた原因を見つけ出し、的確な治療につなげることができます。
ラジオ波『深層筋温熱療法』でどう良くなるの?
『深層筋温熱療法』は、慢性的な肩こりの「悪循環」を断ち切るために、非常に有効なアプローチです。
-
こりの芯(コア)を直接温める ラジオ波の最大の特徴は、体の深部で熱を発生させる「深部加温」です¹¹。「こり」固まった筋肉は、水分が少なくなり線維化しているため、健康な筋肉よりも電気抵抗が高くなっています。ラジオ波は、そのエネルギーが電気抵抗の高い場所に集中するという性質があるため、自動的に「こりの芯」を狙い撃ちし、内側から効率よく温めてくれるのです¹²。
-
血行促進と筋弛緩 深部が3~5℃温められると、圧迫されていた血管が拡張し、血流が劇的に改善します¹¹。新鮮な酸素や栄養が流れ込み、溜まっていた疲労物質が一気に洗い流されます。ある研究では、『深層筋温熱療法』を受けた腰痛患者の81%に痛みの軽減効果が認められたと報告されています⁹。また、温熱効果で硬くなった筋膜や筋肉そのものが柔軟になり、つらい緊張が和らぎます。
-
自律神経を整え、心身をリラックスさせる ラジオ波の深部から伝わる心地よい温かさは、過剰に働いていた交感神経の興奮を鎮め、心身をリラックスさせる副交感神経を優位に導きます。これにより、ストレスによる筋肉の緊張が緩和されます。さらに、この心地よい刺激は、体内で「幸せホルモン」とも呼ばれるセロトニンなどの神経伝達物質の分泌を促す可能性も指摘されており、痛みを和らげるだけでなく、精神的な安らぎをもたらす助けとなります。
『深層筋温熱療法』と当院独自の手技療法を組み合わせることで、表層から深層まで、そして身体から心まで、包括的にアプローチし、長年お悩みのつらい肩こりの根本改善を目指します。
3. 腱板損傷・腱板断裂
どんな症状?どのくらいの人がなるの?
肩の痛みや機能障害の原因として非常に多く、特に中高年の方に増えてくる疾患です。腕を上げたり、後ろに回したりする特定の動きで痛みが出たり、力が入りにくくなったりするのが特徴です。「夜間痛」も代表的な症状で、痛みで目が覚めてしまうことも少なくありません。腕の力は弱くなりますが、反対の手で支えれば腕が上がる点で、関節自体が固まる五十肩とは区別されます。
なぜ痛くなるの?
肩関節には、腕をスムーズに動かし、関節を安定させるために重要な4つの筋肉(棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋)があり、これらの先端にある腱が板状になっているため「腱板」と呼ばれています。この腱板が、加齢によってもろくなったり(変性)、使いすぎや転倒などの外傷によって傷ついたり、切れたり(断裂)するのがこの疾患です。特に棘上筋という腱は、骨と骨の間に挟まれやすい構造のため、最も損傷を受けやすいと言われています。
断裂と聞くと手術が必要だと思われがちですが、断裂があっても約70%の患者様は、リハビリなどの保存療法で症状が改善すると報告されています。これは、残っている腱や周りの筋肉がうまく働くことで、機能を補えるようになるためです。
どんな治療法があるの?
まずは保存療法が基本となります。痛みを引き起こす動作を避け、お薬や注射で炎症と痛みをコントロールしながら施術を行います。リハビリでは、肩が固まらないように動かす練習(可動域訓練)や、残った腱板や肩甲骨周りの筋肉を鍛えて、肩の安定性を取り戻すトレーニングを行います。これらの保存療法で改善が見られない場合や、活動性の高い若い方などでは、関節鏡を使った低侵襲な手術(腱板修復術)が検討されます。
エコー(超音波)で何がわかるの?
エコーは、腱板の状態を観察するのに非常に優れた観察方法です。レントゲンでは写らない腱の断裂の有無、断裂の大きさや場所を、その場で観察することができます¹⁰。最終的な判断はMRI検査などの所見との総合的な判断が必要です。
ラジオ波『深層筋温熱療法』でどう良くなるの?
腱板損傷・断裂に対する『深層筋温熱療法』の有効性については、世界中の研究をまとめた質の高いレビュー(コクランレビューなど)において、「現時点では効果は不確か」と結論付けられています¹³, ¹⁴。これは、「効かない」ということではなく、「効果を証明する質の高い研究がまだ足りない」という状態です¹³。しかし、その理論的な背景から、補助的な治療法として大きな可能性を秘めています。
-
修復環境を整える血流改善 加齢による腱板の変性の背景には、腱への血流が乏しくなることが一因として挙げられています。『深層筋温熱療法』は、深部を加温することで血流を著しく増加させます¹¹。これにより、傷ついた腱の修復に必要な酸素や栄養素を届け、組織が治癒しやすい環境を整える手助けをします¹¹。
-
痛みの緩和と動きの改善 腱板が損傷すると、痛みから肩を動かさなくなり、結果として周りの関節包などが硬くなって、さらに動きが悪くなるという悪循環に陥りがちです。『深層筋温熱療法』は、RETモードを用いることで、腱や関節包のような電気抵抗の高い組織を選択的に温めることができます¹²。温熱効果によって硬くなった組織の柔軟性が高まり、痛みが緩和され、リハビリが行いやすい状態を作ります。個別の研究では、『深層筋温熱療法』が超音波治療よりも短期的に優れた鎮痛効果を示した¹⁵、あるいはステロイド注射と同等の効果を示した¹⁶、といった有望な報告も存在します。
-
運動療法の効果を最大化する 『深層筋温熱療法』は、それ自体が断裂を治すわけではありません。その真価は、治療の主役である運動療法と組み合わせることで発揮されます。温熱療法で血流を改善し、組織を柔らかくしてから運動療法を行うことで、より安全で効果的なリハビリが可能となり、機能回復を促進することが期待されます。
4. 石灰沈着性腱板炎
どんな症状?どのくらいの人がなるの?
40~60代の女性に比較的多く見られる疾患です。ある日突然、何の前触れもなく肩に激痛が走り、腕を全く動かせなくなるのが典型的な症状です。その痛みは「耐え難い」と表現されるほど強烈で、夜も眠れなくなることが多く、救急外来を受診される方も少なくありません。この激しい症状は「急性期」と呼ばれます。一方、腕を上げた時の痛みや引っかかり感など、比較的穏やかな症状が続く「慢性期」もあります。
なぜ痛くなるの?
その名の通り、肩の腱板(特に棘上筋腱)の中に、リン酸カルシウムというチョークの粉や歯磨き粉のような「石灰」が沈着してしまう病気です。なぜ石灰が溜まるのか、正確な原因はまだ完全には解明されていませんが、腱の血行不良や加齢による変性、体質などが関係していると考えられています。 この疾患には特徴的なサイクルがあります。
-
形成期・定着期: 症状がないまま、腱の中に石灰が静かに溜まっていく時期です。
-
吸収期: 体の防御システム(マクロファージなどの免疫細胞)が、この石灰を「異物」と認識して攻撃し、吸収・排除しようとします。この時に非常に強い炎症反応が起こり、激痛を引き起こすのです。つまり、激しい痛みは、体が石灰を治そうとしているサインでもあるのです。
どんな治療法があるの?
激痛を伴う急性期には、まず炎症と痛みを抑えることが最優先です。安静にし、抗炎症薬の飲み薬や、ステロイドと麻酔薬の注射を行います。注射は非常に効果的なことが多いです。痛みが落ち着いた慢性期には、自然な吸収を促す目的で、体外衝撃波療法(ESWT)などが選択されることもあります。ESWTは、石灰を縮小させ痛みを和らげる効果が、質の高い研究で証明されています¹⁷。当院ではESWTは行っておりません。
エコー(超音波)で何がわかるの?
エコーは石灰沈着性腱板炎の診断と治療において、極めて重要な役割を果たします。エコーを使うと、腱の中にある石灰の場所、大きさ、そして性状(硬い石膏状か、柔らかいミルク状かなど)をリアルタイムで詳細に観察できます¹⁰。これにより、現在の病期を正確に把握できます。また、注射を行う際には、エコーで石灰を見ながら直接針を刺し、内部の石灰を吸引・洗浄することも可能で、非常に効果的な治療法となります¹⁰。
ラジオ波『深層筋温熱療法』でどう良くなるの?
『深層筋温熱療法』は、石灰沈着性腱板炎の病期に応じて使い分けることで、治療の大きな助けとなります。
-
慢性期(定着期)の症状緩和と治癒促進 ラジオ波温熱療法の最も良い適応となるのが、鈍い痛みや可動域制限が続く慢性期です。この時期の肩は、石灰の周りの組織が硬くなり、血行も悪くなっています。ラジオ波で深部を加温することで、病変周囲の血流を強力に促進し、硬くなった組織の柔軟性を高めます¹¹。これにより、痛みが緩和されると同時に、体が本来持っている石灰を自然に吸収するプロセスを後押しする環境が整います。
-
急性期の激痛に対する禁忌と応用 激しい炎症が起きている急性期に温熱を加えることは、炎症をさらに悪化させる可能性があるため、原則として禁忌です。しかし、ラジオ波治療器の「非熱モード」を用いれば、熱を発生させずに炎症を調節し、痛みを和らげる効果が期待できます。
5. 肩峰下インピンジメント症候群
どんな症状?どのくらいの人がなるの?
肩の痛みを訴えて医療機関を訪れる方の中で、最も一般的に見られる原因の一つで、肩に関する愁訴の44~65%を占めるとされています。腕を上げ下げする動作の途中、特に腕を横から60°~120°くらい上げた範囲で「ズキッ」とした痛みや引っかかりを感じるのが特徴で、これは「有痛弧徴候(ゆうつうこちょうこう)」と呼ばれます。夜間に痛みが強くなることもあります。
なぜ痛くなるの?
インピンジメントとは「衝突・挟み込み」という意味です。肩を動かすとき、腕の骨(上腕骨)の先端が、屋根のようになっている肩の骨(肩甲骨の一部である肩峰)の下をスムーズに滑り込みます。しかし、この骨と骨の間にある、クッションの役割をする「滑液包」や、筋肉のスジである「腱板」が、何らかの原因で挟み込まれてしまい、繰り返し圧迫・摩擦されることで炎症が起きて痛みが発生します。 原因は大きく二つに分けられます。
-
構造的要因: 生まれつき肩峰の形が下向きに弯曲していたり(フック型)、加齢によって骨のトゲ(骨棘)ができたりして、物理的に隙間が狭くなっているケースです。
-
機能的要因: 肩を支える筋肉(腱板)の機能が低下したり、猫背のような不良姿勢によって肩甲骨の動きが悪くなったりすることで、腕を上げる際に腕の骨がうまく滑らずに上にずり上がり、挟み込みが起きてしまうケースです。
多くの場合、これらの要因が複雑に絡み合い、「挟まる→炎症→痛い→さらに動きが悪くなる→もっと挟まる」という「悪循環」に陥ってしまいます。
どんな治療法があるの?
まずは、痛みを引き起こす動作を避けて安静にし、お薬や注射で炎症を抑えながら、挟み込みが起きないような正しい肩の使い方を学ぶ運動療法を行うのが基本です。こうした保存療法で改善しない難治性の場合は、関節鏡を使って挟み込みの原因となっている骨のトゲを削る手術(肩峰下除圧術)が検討されることもあります。ある研究では、手術(ASD)にラジオ波を追加しても、追加しない場合と比べて1年後の結果に差はなかったと報告されており、ラジオ波はまず保存療法の一環としてその価値を発揮すると考えられます¹⁹。
エコー(超音波)で何がわかるの?
エコー検査では、炎症を起こして腫れている滑液包や、傷んでいる腱板の状態を詳しく観察できます¹⁰。さらに、エコーの最大の利点は、実際に腕を動かしながら、どの角度で、どのように腱板や滑液包が挟み込まれているのかをリアルタイムで動画として確認できることです。これにより、インピンジメントの原因を正確に特定し、一人ひとりに合った効果的な施術計画を立てることが可能になります。
ラジオ波『深層筋温熱療法』でどう良くなるの?
『深層筋温熱療法』は、インピンジメント症候群が引き起こす「痛みの悪循環」を断ち切る上で、優れた効果を発揮することが科学的な研究でも示されています。
-
痛みの緩和と機能の改善 質の高い研究(ランダム化比較試験)において、ラジオ波温熱療法(特に経皮的パルスRFという方法)を行うと、偽の治療を行ったグループに比べて、安静時の痛みと、日常生活における肩の障害の程度(SPADIスコア)が有意に改善したことが報告されています³。これは、ラジオ波が痛みを和らげるだけでなく、実際の生活のしやすさに直結する機能回復に貢献することを示しています³。
-
運動療法との相乗効果 『深層筋温熱療法』は、深部を加温することで炎症を起こしている組織の血流を改善し、痛みの原因物質を洗い流すとともに、硬くなった組織の柔軟性を高めます¹¹。ただし、動作時の痛みを根本的に解決するためには、インピンジメントを起こす原因となっている筋肉のアンバランスや不良動作を修正する運動療法が不可欠です。ラジオ波でまず痛みと組織の硬さを取り除き、動きやすい状態を作ってから運動療法を行う。この二人三脚のアプローチこそが、インピンジメント症候群の根本改善への最短ルートと言えるでしょう。
【電話でのご予約・お問い合わせ】
TEL:050-3649-4281
【Webからのご予約はこちら】
右下の予約ボタンから予約可能です。
引用文献一覧
以下は、本ページを作成するにあたり参考にした主要な学術論文です。
-
Hsu HY, et al. (2022). Clinical Guidelines in the Management of Frozen Shoulder: An Update! J Clin Med.
-
要約: 肩関節周囲炎(五十肩)の管理に関する臨床ガイドラインの更新版です。本疾患が関節包の炎症と線維化を特徴とする病態であることを解説しており、病態理解の根拠となります。
-
-
Chan HBY, et al. (2017). The effectiveness of therapeutic ultrasound for frozen shoulder. Clin Rehabil.
-
要約: 五十肩に対する治療的超音波の効果を検証したレビューです。本文書では、五十肩の典型的な症状である夜間痛や可動域制限についての一般的な記述の参考としています。
-
-
Gür Ş, et al. (2024). Efficacy of Transcutaneous Pulsed Radiofrequency Treatment in Subacromial Impingement Syndrome: A Randomized Controlled Study. Pain Res Manag.
-
要約: 肩峰下インピンジメント症候群に対する経皮的パルスラジオ波(TCPRF)治療の有効性を検証したRCT。偽治療と比較し、安静時痛と機能障害を有意に改善することを実証しました。
-
-
Lewis J. (2015). Rotator cuff tendinopathy/subacromial impingement syndrome: is it time for a new method of assessment? Br J Sports Med.
-
要約: 腱板関連の肩痛に関するレビュー論文。肩関節周囲炎の治療法として、病期に応じた運動療法や注射療法が標準的であることを示しています。
-
-
Uzun T, et al. (2024). Impact of TECAR therapy on pain and function in adhesive capsulitis: a randomized controlled trial. Int Orthop.
-
要約: 五十肩患者に対し、標準理学療法にTECAR療法(ラジオ波温熱)を併用すると、痛みと機能が有意に改善することを示したRCTです。
-
-
Rezaian M, et al. (2024). Restoring Shoulder Function: A Randomized Clinical Trial of TECAR Therapy for Frozen Shoulder. Iran Biomed J.
-
要約: 五十肩患者に対するTECAR療法の有効性を検証したRCT。薬物療法へのTECAR療法の追加が、痛みと機能障害の両方で優れた改善をもたらすことを示しました。
-
-
Abdel-aziem AA, et al. (2014). Ultrasound-guided pulsed radiofrequency stimulation of the suprascapular nerve for adhesive capsulitis: a prospective, randomized, controlled trial. Pain Pract.
-
要約: 五十肩患者に対し、パルス状ラジオ波(PRF)と理学療法の併用が、理学療法単独よりも痛みを軽減するまでの期間を著しく短縮させることを示したRCTです。
-
-
Chen CY, et al. (2024). Effect of pulsed radiofrequency to the suprascapular nerve (SSN) in treating frozen shoulder pain: A randomised controlled trial. Int J Clin Pract.
-
要約: 五十肩の痛みに対する肩甲上神経へのPRF治療が、薬物療法と比較して痛みと機能を劇的に改善させることを示したRCTです。
-
-
Takahashi K, et al. (1999). Clinical effect of capacitive electric transfer hyperthermia therapy for lumbago. J Phys Ther Sci.
-
要約: ラジオ波温熱療法(容量性電気転送温熱療法)の腰痛に対する臨床効果を報告した論文。患者の81%に痛みの軽減効果が見られたとしており、ラジオ波の鎮痛効果の根拠となります。
-
-
Lin MT, et al. (2020). The effectiveness of ultrasound-guided office-based procedures for the management of rotator cuff-related shoulder pain: a systematic review and meta-analysis. Kaohsiung J Med Sci.
-
要約: 腱板関連の肩痛に対するエコーガイド下治療の有効性を評価したレビュー。エコーが診断と治療介入の精度を高める上で有用であることを示しています。
-
-
Giombini A, et al. (2008). Hyperthermia induced by microwave diathermy in the management of muscle and tendon injuries. Br J Sports Med.
-
要約: 筋肉や腱の損傷管理におけるマイクロ波ジアテルミー(ラジオ波温熱の一種)による温熱療法をレビューした論文。深部加温による血流増加や疼痛緩和といった作用機序を解説しています。
-
-
Navarro-Ledesma S, et al. (2023). Effects of capacitive-resistive electric transfer in the management of musculoskeletal pain: A systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore).
-
要約: 筋骨格系の痛みに対するラジオ波温熱療法(CRET/TECAR)の効果をまとめたシステマティックレビュー。RETモードが腱や関節包などの高抵抗組織を対象とすることを示しています。
-
-
Page MJ, et al. (2021). Electrotherapy modalities for rotator cuff disease. Cochrane Database Syst Rev.
-
要約: 腱板疾患に対する電気療法を評価した最も権威のあるコクランレビュー。現時点での研究では、マイクロ波ジアテルミー(ラジオ波温熱の一種)の有効性は不確かであると結論付けています。
-
-
Negrini S, et al. (2023). The Efficacy of Electromagnetic Diathermy for the Treatment of Musculoskeletal Disorders: A Systematic Review. J Clin Med.
-
要約: 筋骨格系疾患に対する電磁ジアテルミー(ラジオ波温熱を含む)の有効性を評価した最新のシステマティックレビュー。結果は一貫しておらず、エビデンスが不足していると指摘しています。
-
-
Giombini A, et al. (2006). Short-term effectiveness of hyperthermia for supraspinatus tendinopathy in athletes: a short-term randomized controlled study. Am J Sports Med.
-
要約: アスリートの棘上筋腱板症に対し、マイクロ波温熱療法が超音波治療や運動療法単独よりも短期的に優れた効果を示したとするRCTです。
-
-
Rabini A, et al. (2012). Effects of local microwave diathermy on shoulder pain and function in patients with rotator cuff tendinopathy in comparison to subacromial corticosteroid injections: a single-blind randomized trial. J Orthop Sports Phys Ther.
-
要約: 腱板腱板症患者に対し、マイクロ波温熱療法がステロイド注射と同等の疼痛・機能改善効果をもたらしたことを示したRCTです。
-
-
Gerdesmeyer L, et al. (2003). Extracorporeal shock wave therapy for the treatment of chronic calcifying tendonitis of the rotator cuff: a randomized controlled trial. JAMA.
-
要約: 慢性石灰沈着性腱板炎に対する体外衝撃波療法(ESWT)の有効性を検証した質の高いRCT。ESWTが石灰の吸収を促進し、痛みを軽減することを示しました。
-
-
Kim JS, et al. (2012). Pulsed radiofrequency lesioning of the axillary and suprascapular nerves in a patient with intractable calcific tendinitis. J Anesth.
-
要約: 他の治療法に抵抗した難治性の石灰沈着性腱板炎に対し、パルス状ラジオ波(PRF)が劇的な改善をもたらした症例報告。PRFが自己治癒メカニズムの引き金となる可能性を提示しています。
-
-
Taverna E, et al. (2013). Is radiofrequency treatment effective for shoulder impingement syndrome? a prospective randomized controlled study. Arthroscopy.
-
要約: 肩峰下インピンジメント症候群に対する関節鏡視下手術にラジオ波治療を追加する効果を検証したRCT。1年後の時点では、追加による上乗せ効果は認められなかったと報告しています。
-
※ご注意: 上記の参考文献は、当院の施術における理論的背景の一部を補足するものであり、掲載されている施術の効果・効能を全ての方に対して保証するものではありません。

図1
股関節
肩関節

図2
.png)
図3
.png)
図4
_edited.jpg)
図8

図9
.png)
図5
.png)
図6
.png)
図7
