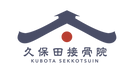
~肩、首、腰の接骨院~
本質と向き合い、健やかな未来を創る
~首の痛み~
なぜあなたの首は痛むのか?
首の専門家が解き明かす「痛みの正体」
首(頸椎)の機能解剖学
1.ボーリングの球を支える繊細な柱:頸椎(けいつい)
私たちの首の骨、専門的には頸椎(けいつい)と呼ばれますが、これは7つの骨が積み木のように重なってできています¹。そして、この細い骨の上には、体重の約10%(成人で約5kg)もある重たい頭が乗っています¹。これはまるで、細い柱の上でボーリングの球を支えているようなものです。
この不安定な構造を安定させ、しなやかに動かすために、首には様々な仕組みが備わっています。
-
理想的なS字カーブ 健康な人の首の骨を横から見ると、緩やかな前カーブ(前弯)を描いています。このカーブがバネのような役割を果たし、歩行やジャンプの際に頭にかかる衝撃を巧みに吸収・分散してくれるのです¹。しかし、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用でうつむき姿勢が続くと、このカーブが失われ「ストレートネック」と呼ばれる状態になり、頭の重みが直接首や肩にかかることで、様々な不調の引き金となります。
2.骨と骨の間の衝撃吸収材:椎間板(ついかんばん)
7つの首の骨と骨の間には、椎間板(ついかんばん)という軟骨でできたクッションが挟まっています。これは、中心にあるゼリー状の髄核(ずいかく)と、それを頑丈な線維の層で包んだ線維輪(せんいりん)からできています。よく「あんパン」に例えられますが、外側のパンが線維輪、中のあんこが髄核です。
この椎間板が衝撃を吸収してくれるおかげで、私たちはスムーズに首を動かすことができます。しかし、加齢や悪い姿勢によって椎間板の水分が失われて弾力性が低下したり、線維輪に亀裂が入って中の髄核が飛び出してしまったりすることがあります。これが「頸椎椎間板ヘルニア」です。
3.首を支え、動かす立役者:たくさんの筋肉たち
首の周りには、大小さまざまな筋肉が何層にも重なり合って、頭と首を支え、動かしています。
-
アウターマッスル(表層筋):僧帽筋や胸鎖乳突筋など、外側にある大きな筋肉で、首を動かすパワフルな役割を担います¹⁹。いわゆる「肩こり」や「首こり」で硬くなりやすい筋肉です。
-
インナーマッスル(深層筋):頭板状筋や頸長筋など、骨の近くにある小さな筋肉で、頸椎の安定性を保つ「天然のコルセット」のような重要な役割を果たします¹⁹。
これらの筋肉が疲労したり、緊張し続けたりすることで血行が悪くなると、痛みやこりを引き起こします。
4.全身につながる情報のハイウェイ:神経と血管
首が「体の司令塔」とも言われる最も重要な理由が、神経と血管が集中している点です。
-
脊髄(せきずい)と神経根(しんけいこん) 首の骨の中には、脳と体をつなぐ非常に太い神経の束である脊髄が通っています。そして、骨と骨の間からは、腕や手、肩などに向かう神経根という神経の枝が分岐しています¹⁷。首に問題が起きると、この神経が圧迫されたり刺激されたりして、痛みやしびれが腕や手にも現れるのです¹⁸。
-
自律神経(じりつしんけい) 首の周辺、特に筋肉の深い部分には、心拍、血圧、呼吸、消化、体温調節など、生命維持に不可欠な機能をコントロールする自律神経(交感神経と副交感神経)の重要な中継地点が存在します。そのため、首の筋肉が過度に緊張すると、この自律神経のバランスが乱れ、頭痛、めまい、吐き気、動悸、全身の倦怠感といった、一見すると首とは無関係に思える全身の不調を引き起こすことがあるのです。
-
椎骨動脈(ついこつどうみゃく) 脳に血液を送る重要な血管の一つである椎骨動脈は、頸椎のすぐそばを走行しています。首の状態が悪化すると、この血流に影響が及び、めまいやふらつきの原因となることもあります。
5.まとめ:首は全身の健康を映す鏡
このように、私たちの首は「骨・椎間板・筋肉・神経・血管」といった多くの要素が、まるで精密機械のように連携しあって機能しています。この精巧なバランスが、不良姿勢、外傷、ストレスなど、何らかの原因で崩れると、痛みやこりだけでなく、全身の様々な不調となって現れます。久保田接骨院では、患者様一人ひとりのお話を丁寧に伺い、なぜその症状が出ているのか、この複雑な首の構造のどこに問題があるのかを的確に見極めることから治療を始めます。
各疾患の解説
1. 「寝違え」(急性頸部痛)と「首・肩のこり」(頸部筋・筋膜性疼痛)
どのような状態?(病態と原因)
「寝違え」は、医学的には「急性疼痛性頸部拘縮」などと呼ばれます。睡眠中に不自然な姿勢が続いたり、体が冷えたりすることで、首の筋肉や靭帯に微細な傷(肉離れに近い状態)や炎症が起きた状態です。
一方、慢性的な「首・肩のこり」は、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用による不良姿勢、精神的なストレスなどが原因で、首周りの筋肉が常に緊張している状態です。この緊張が続くと、筋肉内の血流が悪くなり(虚血)、酸素や栄養が不足し、痛みや疲労の原因となる物質が溜まってしまいます。この「筋肉の緊張 → 血流悪化 → 痛みの発生 → さらなる緊張」という悪循環が、つらい症状の正体です¹⁶。
どんな人がなりやすい?(疫学)
「首筋・肩こり」は非常にありふれた症状で、ある調査では女性の約76%が悩んでいると報告されています。特にデスクワークやストレスの多い現代人にとって、誰にでも起こりうる国民的な悩みと言えます。
一般的な治療法
「寝違え」の直後(急性期)は、炎症を抑えるために安静にし、冷やすことが基本です。無理に動かしたり、強く揉んだりすると悪化することがあります。慢性的なこりに対しては、温めて血行を良くしたり、ストレッチや運動療法が行われます。
エコーで何がわかるの?
柔道整復師は診断を行いませんが、エコーを用いて体の内部を「観察」することで、より安全で的確な施術計画を立てることができます。寝違えやこりの場合、筋肉が炎症を起こして腫れていないか、筋膜が分厚くなっていないかなどをリアルタイムで観察します。これにより、問題となっている箇所を正確に把握し、ラジオ波を当てるべき最適な場所や深さを見極めることができます。
ラジオ波『深層筋温熱療法』でどう良くなるの?
ラジオ波温熱療法は、寝違えや慢性のこりの「痛みの悪循環」を断ち切るために、非常に有効なアプローチが期待できます。
-
体の芯から温め、筋肉をほぐす: ラジオ波は、ホットパックのように表面から熱を加えるのではなく、体の内部で熱を発生させる「深部加温」が最大の特徴です。これにより、手では届かない深層の硬くなった筋肉や筋膜を直接温め、柔軟性を高めることができます¹⁴。組織の温度が3~5℃上昇することで、ガチガチに固まった筋肉が芯から緩んでいきます¹⁴。
-
血流を劇的に改善し、痛みの原因物質を洗い流す: 深部が温まることで血管が拡張し、血流が大幅に増加します¹⁴。これにより、溜まっていた乳酸や痛みの原因となる物質(発痛物質)が効率よく洗い流され、新しい酸素や栄養が細胞に届けられます。
-
脳に働きかけ、痛みを抑える: 心地よい深部の温熱刺激は、痛みの信号を脳に伝えにくくする「ゲートコントロール」という仕組みに働きかけます。さらに、脳自身が持つ鎮痛システム(下行性疼痛抑制系)を活性化させ、痛みを感じにくくする効果も期待できます³˒ ¹⁸。
このように、ラジオ波温熱療法は「①筋肉を緩める」「②血流を改善する」「③痛みを抑える」という3つの作用で、つらい症状の根本原因へのアプローチを目指します。
2. 頸椎症(変形性頸椎症)
どのような状態?(病態と原因)
主に加齢により、首の骨(頸椎)と骨の間でクッションの役割をしている椎間板がすり減ったり、骨のフチにとげ(骨棘:こつきょく)ができたりして、首の痛みや動かしにくさが生じる状態です。この骨のとげが、近くを通る神経を刺激すると、腕や手にしびれや痛みが出ることがあります。
どんな人がなりやすい?(疫学)
加齢が主な原因のため、特に50代以降の中高年の方に多く見られます。長年、首に負担のかかる姿勢や仕事をしてきた方もなりやすい傾向があります。
一般的な治療法
痛みや炎症を抑える薬、首の筋肉をほぐすリハビリテーション、首を支えるカラーの装着といった保存療法が中心です。症状を悪化させないよう、日常生活での姿勢に気をつけることも重要です。
エコーで何がわかるの?
骨の変形そのものはレントゲンで確認しますが、エコーでは神経の通り道周辺の血流の状態や、筋肉が硬くなっていないか、厚くなっていないかを観察します。これにより、どの筋肉の緊張が症状を強くしているのかを把握し、的を絞った施術に繋げます。
ラジオ波『深層筋温熱療法』でどう良くなるの?
ラジオ波温熱療法は、頸椎症の骨の変形そのものを元に戻すことはできません。しかし、変形によって引き起こされる二次的な症状、つまり**「痛み」と「こり」を和らげる**ことに大きな効果が期待できます。
-
こり固まった筋肉へのアプローチ: 骨の変形があると、首や肩の筋肉は常に過剰な負担を強いられ、慢性的に緊張し、血行不良に陥っています。ラジオ波でこれらの筋肉を深部から温めることで、緊張を和らげ、血流を促進します¹⁴。これにより、痛みや重だるさといった不快な症状の緩和を目指します。
-
関節の動きを滑らかに: 首周りの関節を包む組織(関節包)も、加齢とともに硬くなりがちです。ラジオ波で温めることで、これらの組織の柔軟性が高まり、首の動かせる範囲が広がる効果も期待できます¹。
3. 頚椎椎間板ヘルニア
どのような状態?(病態と原因)
背骨のクッションである椎間板の中にある、ゼリー状の髄核という組織が、外側の線維輪という膜を破って飛び出してしまう状態です⁶。この飛び出した髄核(ヘルニア)が、脊髄から枝分かれする神経(神経根)を圧迫したり、化学的な刺激によって強い炎症を起こしたりすることで、首の痛みや、腕から指先にかけての鋭い痛みやしびれを引き起こします⁶。
どんな人がなりやすい?(疫学)
腰のヘルニアと同様に、20代から50代の比較的若い世代に多く、男性に多い傾向があります。悪い姿勢での作業や、スポーツなども発症のきっかけとなります。
一般的な治療法
多くの場合は、手術をしない保存療法で改善が見込めます。痛み止めや、神経の炎症を抑える薬、リハビリテーションが行われます。ヘルニアは自然に小さくなることも多く、まずは安静と適切な保存療法が第一選択となります。
エコーで何がわかるの?
ヘルニアの確定診断はMRIで行いますが、エコーでは神経の周りで炎症が起きて血流が増えていないか、症状に関連する筋肉が過度に緊張していないかを観察します。これにより、現在の症状が筋肉性のものなのか、神経性のものなのかを判断する一助とし、最適な施術方針を立てます。
ラジオ波『深層筋温熱療法』でどう良くなるの?
ラジオ波温熱療法は、飛び出したヘルニアそのものを引っ込める治療ではありません。しかし、ヘルニアによって引き起こされる二次的なつらい症状を和らげるための重要な役割を担います。
-
「痛みの悪循環」を断つ: ヘルニアによる神経の圧迫や炎症は、首や肩の筋肉に強い防御的な緊張(こり)を引き起こします。この二次的な筋肉の痛みが、本来のヘルニアの痛みと合わさって、症状をさらに悪化させていることが少なくありません。ラジオ波温熱療法は、このヘルニア周辺のこり固まった筋肉を深部から温めて血流を改善し、筋肉由来の痛みを和らげます¹˒ ²。
-
回復しやすい環境づくり: 患部周辺の血行が良くなることで、炎症を抑える物質が運ばれやすくなり、組織の回復をサポートします¹⁴。
当院で行うラジオ波温熱療法は、あくまでヘルニアの症状に伴う筋緊張や血行不良を改善し、患者様の苦痛を和らげ、体が本来持つ回復力を高めることを目的としています。
4. むち打ち損傷(外傷性頸部症候群)
どのような状態?(病態と原因)
追突事故などで頭が激しく前後に振られる「むち打ち運動」によって、首の筋肉、靭帯、関節包といった軟部組織が、目に見えないレベルで損傷した状態です¹¹。受傷直後は興奮していて症状を感じにくく、数時間後から翌日にかけて首の痛み、頭痛、肩こり、吐き気、めまいなど多彩な症状が現れるのが特徴です。
どんな人がなりやすい?(疫学)
自動車の追突事故が最も一般的ですが、ラグビーや柔道などのコンタクトスポーツや、転倒などでも発生します。
一般的な治療法
受傷直後の急性期は、炎症を抑えるために安静やカラー固定、冷却が中心です。ただし、過度な安静はかえって回復を遅らせることも分かっており、適切な時期から運動療法などを始めることが重要とされています¹⁰。その後は温熱療法や電気療法、リハビリテーションで機能回復を目指します。
エコーで何がわかるの?
骨に異常がないかを確認するのはレントゲンの役割ですが、エコーではむち打ち損傷の主座である軟部組織(筋肉や靭帯)の状態を詳しく見ることができます。筋肉の微細な断裂や内出血、炎症の程度などを観察し、損傷の度合いを正確に把握することで、安全かつ効果的な施術計画(いつから温めるべきか、どのくらいの強さでアプローチするかなど)を立てることが可能になります。
ラジオ波『深層筋温熱療法』でどう良くなるの?
むち打ち損傷では、ホットパックなどの表面的な温熱では届かない、首の深層部にある筋肉や関節、靭帯が傷ついています。ラジオ波温熱療法は、こうした深部の損傷組織に直接アプローチできる点で非常に優れていると考えられます。
-
深部組織の修復を促進: 深部を加温することで、傷ついた組織への血流を増やし、酸素や栄養を送り届けて修復プロセスを加速させます¹⁴。筋損傷後の回復を早める効果も報告されています⁵。
-
痛みの悪循環を断ち切り、慢性化を防ぐ: 損傷による痛みは、防御的に筋肉を硬直させ、血流を悪化させて回復を妨げます。ラジオ波で深部から温め、筋肉の緊張を解き、血流を改善することで、この悪循環を断ち切ることを目指します。これにより、症状の慢性化を防ぎ、早期の回復が期待できます。
-
硬くなった組織を柔軟に: 時間が経って硬くなった筋肉や関節包も、温めることで柔軟性を取り戻し、首の動き(可動域)の改善につながります¹²。
5. 胸郭出口症候群(TOS)
どのような状態?(病態と原因)
首から腕や手に向かう神経の束(腕神経叢)や血管が、通り道である「胸郭出口」という狭いスペースで、周りの筋肉や骨によって圧迫されて起こる症状の総称です²⁰。圧迫が起こりやすい場所は主に3つあり、首の筋肉(斜角筋)の間、鎖骨と第一肋骨の間、胸の筋肉(小胸筋)の下などが挙げられます²⁰。
どんな人がなりやすい?(疫学)
「なで肩」で筋肉が少ない女性(神経が下に引っ張られる牽引型)や、逆に筋肉質で「いかり肩」の男性(筋肉で圧迫される圧迫型)に多いとされています。長時間のデスクワークなどによる猫背姿勢も、胸の筋肉を硬くさせ、発症の大きな原因となります。
一般的な治療法
手術が必要なケースはまれで、ほとんどが保存療法で改善を目指します。原因となっている筋肉(斜角筋や小胸筋など)の緊張を和らげるストレッチ、肩甲骨周りの筋力を強化して正しい姿勢を保つ運動療法、症状を誘発する動作を避ける生活指導などが中心となります。
エコーで何がわかるの?
エコーを使うと、神経や血管と、それを圧迫している可能性のある筋肉との位置関係をリアルタイムで観察できます。例えば、腕を上げ下げする動きの中で、筋肉が神経や血管をどのように圧迫するのかを動的に見ることも可能です。これにより、どの筋肉が最も問題となっているのかを特定し、より的確なラジオ波の照射やストレッチ指導に繋げることができます。
ラジオ波『深層筋温熱療法』でどう良くなるの?
胸郭出口症候群の根本原因の一つは、神経や血管を圧迫している深層の筋肉の緊張です¹⁶。ラジオ波温熱療法は、この原因に直接アプローチできる非常に有効な手段です。
-
原因筋をピンポイントで温め、圧迫を解放: ラジオ波、特にRETモードと呼ばれる方法は、電気抵抗の高い硬くなった組織を選択的に温める特性があります¹²。これにより、圧迫の原因となっている斜角筋や小胸筋といった、体の奥深くにある硬い筋肉をピンポイントで加温できます。筋肉が深部から温まり、緊張が解けることで、神経や血管への物理的な圧迫が軽減され、しびれや痛みの緩和が期待できます²。
-
圧迫されていた神経・血管の回復を助ける: 圧迫されていた部位の血流が改善することで、神経や血管に十分な酸素と栄養が供給され、組織の回復をサポートします¹⁴。
ストレッチや運動療法だけではなかなか緩まない深層の筋肉に直接アプローチできるのが、ラジオ波温熱療法の大きな利点の一つです。
【電話でのご予約・お問い合わせ】
TEL:050-3649-4281
【Webからのご予約はこちら】
右下の予約ボタンから予約可能です。
引用文献一覧
以下は、このページを作成するにあたり参考にした学術論文の一部です。私たちの施術が科学的な根拠に基づいていることを示すものです。
-
Navarro-Ledesma, S., et al. (2024). The Effects of Manual Therapy with TECAR Therapy, on Pain, Disability and Range of Motion in Women with Non-specific Chronic Neck Pain. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran.
-
要約: 慢性の首の痛みを持つ女性に対し、徒手療法にラジオ波温熱療法(TECAR)を併用すると、徒手療法単独よりも痛みの軽減効果が高いことを示したランダム化比較試験(RCT)。
-
-
Daneshmandi, H., et al. (2024). Effect of Adding Transfer Energy Capacitive and Resistive Therapy to Conventional Therapy for Patients With Myofascial Pain Syndrome in Upper Trapezius. Journal of Clinical Medicine.
-
要約: 肩こりの原因となる僧帽筋の筋膜性疼痛症候群の患者に対し、従来の治療にラジオ波温熱療法を追加することで、痛みや機能障害が大幅に改善することを示したRCT。
-
-
Yasui, H., et al. (2010). Significant correlation between autonomic nervous activity and cerebral hemodynamics during thermotherapy on the neck. Autonomic Neuroscience.
-
要約: 首を温めることが、脳の特定領域(前頭前野)の活動を落ち着かせ、自律神経のバランスをリラックス状態(副交感神経優位)にシフトさせることを客観的データで示した研究。
-
-
Lee, J. H., et al. (2021). Therapeutic effects of capacitive and resistive electric transfer in patients with chronic low back pain. Journal of Physical Therapy Science.
-
要約: 慢性の腰痛患者において、ラジオ波温熱療法が偽治療と比較して、痛みの強さと筋肉の硬さを有意に低下させたことを示したRCT。
-
-
Tsuchiya, R., et al. (2022). The Effect of Capacitive and Resistive Electric Transfer Intervention on Delayed-Onset Muscle Soreness Induced by Eccentric Exercise. International Journal of Environmental Research and Public Health.
-
要約: いわゆる「筋肉痛」に対し、ラジオ波温熱療法が介入後に痛み、筋力低下、関節の動きの制限を有意に改善させたことを示した研究。むち打ち損傷などの微細な筋損傷の回復促進につながる可能性を示唆。
-
-
Ge, H. Y., et al. (2023). CT-guided Pulsed Radiofrequency Combined with Steroid Injection for Sciatica from Herniated Disk: A Randomized Trial. Radiology.
-
要約: 椎間板ヘルニアによる坐骨神経痛に対し、パルス高周波(ラジオ波を用いた神経ブロックの一種)とステロイド注射の併用が、ステロイド単独よりも長期的な痛みの軽減と機能改善をもたらしたことを示す質の高いRCT。
-
-
Vallejo, R., et al. (2017). Pulsed radiofrequency in the treatment of spinal conditions: a review of the literature. British Journal of Anaesthesia.
-
要約: 脊椎関連の痛みに対するパルス高周波療法の有効性に関する文献をレビューし、その有用性を示唆しつつ、今後の研究課題を提示した論文。
-
-
Urrútia, G., et al. (2007). Percutaneous thermocoagulation intradiscal techniques for discogenic low back pain. Spine.
-
要約: 椎間板性の腰痛に対するラジオ波を用いた椎間板内治療(焼灼術)は、偽治療と比較して有効であるという質の高いエビデンスは存在しないと結論付けた、初期のシステマティックレビュー。
-
-
Zhang, T., et al. (2023). Percutaneous Intradiscal Radiofrequency Thermocoagulation Combined with Sinuvertebral Nerve Ablation for the Treatment of Discogenic Low Back Pain. Pain Physician.
-
要約: 従来型の椎間板内ラジオ波焼灼術に、痛みを伝える神経の焼灼を追加することで、治療効果が有意に高まる可能性を示した新しいアプローチの研究。
-
-
Rosenfeld, M., et al. (2003). Active intervention in patients with whiplash-associated disorders improves long-term prognosis: a randomized controlled clinical trial. Spine (Phila Pa 1976).
-
要約: むち打ち損傷の患者において、安静にするよりも早期から積極的な運動療法を開始した方が、長期的な予後が良好であったことを示すRCT。
-
-
Seferiadis, A., et al. (2004). A review of treatment interventions in whiplash-associated disorders. European Spine Journal.
-
要約: むち打ち関連障害に対する様々な治療介入をレビューした論文。ラジオ波神経焼灼術が特定の患者群に有効であることを示している。
-
-
Glimmerveen, A., et al. (2020). Capacitive and resistive electric transfer therapy in rehabilitation: a systematic review. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation.
-
要約: リハビリテーションにおけるラジオ波温熱療法のシステマティックレビュー。多くの研究で肯定的な結果が示されているものの、研究デザインの質の向上が今後の課題であると指摘。
-
-
Forouzan, A., et al. (2024). The effects of capacitive and resistive energy transfer therapy on pain and function in athletes with chronic adductor-related groin pain. BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation.
-
要約: アスリートの慢性的な股関節痛に対し、ラジオ波温熱療法が痛みと機能の改善に有効であることを示した論文。
-
-
Clijsen, R., et al. (2020). Does the Application of Tecar Therapy Affect Temperature and Perfusion of the Skin and Muscle Microcirculation? A Pilot Feasibility Study on Healthy Subjects. The Journal of Alternative and Complementary Medicine.
-
要約: ラジオ波温熱療法(TECAR)が、皮膚や筋肉の微小循環における血流量を増加させ、組織温度を上昇させることを客観的に示した研究。
-
-
Wallis, B. J., et al. (1997). Resolution of psychological distress of whiplash patients following treatment by radiofrequency neurotomy: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Pain.
-
要約: 慢性のむち打ち症状を持つ患者に対し、ラジオ波神経焼灼術が痛みだけでなく、それに伴う心理的な苦痛も解消することを示したRCT。
-
-
Money, S. (2017). Pathophysiology of Myofascial Pain. Current Pain and Headache Reports.
-
要約: 筋膜性疼痛(こりの原因)の病態生理について解説したレビュー論文。胸郭出口症候群の病態理解にも関連する。
-
-
Kassab, M. P., et al. (2023). Autonomic nervous system and endocrine system response to upper and lower cervical spine mobilization in healthy male adults: a randomized crossover trial. BMC Musculoskeletal Disorders.
-
要約: 首への徒手的なアプローチが、自律神経系とストレスホルモン(コルチゾール)の反応を鎮静化させることを示した研究。
-
-
Morikawa, Y., et al. (2017). Compression at Myofascial Trigger Point on Chronic Neck Pain Provides Pain Relief through the Prefrontal Cortex and Autonomic Nervous System: A Pilot Study. Frontiers in Neuroscience.
-
要約: 慢性の首の痛みに対し、トリガーポイント(痛みの引き金点)への圧迫が脳(前頭前野)と自律神経系を介して痛みを和らげることを示した研究。
-
-
Effectiveness of TECAR Therapy for Managing Pain in Sports-Related Musculoskeletal Pathologies: A Systematic Review with Meta-analysis. (2024). Medical Journal of the Islamic Republic of Iran.
-
要約: スポーツ関連の筋骨格系の痛みに対するラジオ波温熱療法(TECAR)の有効性を検証したメタアナリシス。対照群と比較して有意な疼痛軽減効果を示した。
-
-
Ishida, T., et al. (2024). Intractable pain due to thoracic outlet syndrome successfully treated with percutaneous epidural adhesiolysis. Surgical Case Reports.
-
要約: 胸郭出口症候群による難治性の痛みに対する治療の症例報告。専門的な治療法についての知見を提供する。
-
※ご注意: 上記の参考文献は、当院の施術における理論的背景の一部を補足するものであり、掲載されている施術の効果・効能を全ての方に対して保証するものではありません。