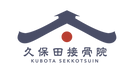
~肩、首、腰の接骨院~
本質と向き合い、健やかな未来を創る
~腰の痛み~
なぜあなたの腰は痛むのか?
腰の専門家が解き明かす「痛みの正体」
腰(腰椎)の機能解剖学
「腰が痛い」と一言で言っても、その原因は様々です。なぜなら、腰はたくさんの骨や筋肉、神経などが複雑に組み合わさってできている、とても重要な場所だからです。ご自身の腰の痛みを正しく理解するために、まずは腰がどのような構造になっているのか、一緒に学んでいきましょう。
1. 腰の土台となる「骨」たち
腰の骨は、専門的には「腰椎(ようつい)」と呼ばれ、5つの骨が積み木のように重なってできています。この腰椎は、上半身の重みを支えながら、体をひねったり曲げたりする動きを可能にする、まさに体の要です。
-
椎骨(ついこつ): 積み木の一つひとつの骨のことです。前に丸い部分(椎体)があり、後ろには突起があります。
-
椎間板(ついかんばん): 椎骨と椎骨の間にある、軟骨でできたクッションです。ゼリー状の髄核(ずいかく)とその周りを丈夫な線維輪(せんいりん)が囲んでいます¹。このクッションのおかげで、歩いたりジャンプしたりするときの衝撃を和らげてくれます。しかし、加齢や負担によってこのクッションが飛び出してしまうことがあり、これが椎間板ヘルニアの原因となります。
-
脊柱管(せきちゅうかん): 椎骨が連なってできる、トンネル状の空間です。この中には、脳から足へと続くとても大切な神経の束が通っています。このトンネルが何らかの原因で狭くなり、中の神経が圧迫されるのが脊柱管狭窄症です。
-
椎間関節(ついかんかんせつ): 椎骨の後ろ側にある小さな関節で、背骨の滑らかな動きを助けています。この関節に負担がかかり炎症を起こすと、痛みの原因(椎間関節性腰痛)になることがあります。
-
仙骨(せんこつ)と腸骨(ちょうこつ): 5つの腰椎の下には、手のひらのような形をした「仙骨」という骨があります。そして、その両脇にあるのが骨盤を形成する「腸骨」です。
-
仙腸関節(せんちょうかんせつ): 仙骨と腸骨をつなぐ関節です。数ミリしか動かない非常に安定した関節ですが、出産や中腰での作業などで負担がかかると、ズレや炎症が生じ、仙腸関節性腰痛という頑固な痛みを引き起こすことがあります。
2. 体を動かす「筋肉」
腰の周りには、体を支えたり動かしたりするためのたくさんの筋肉があります。これらの筋肉が硬くなったり、弱くなったりすることも腰痛の大きな原因です。
-
インナーマッスル(深層筋): 体の奥深くにあって、背骨を直接支える重要な筋肉です。代表的なものに多裂筋(たれつきん)や腹横筋(ふくおうきん)があります。これらの筋肉がしっかり働くことで、背骨が安定し、腰への負担が減ります。ラジオ波温熱療法は、体の深部まで熱を届けることができるため、このようなインナーマッスルに直接アプローチして、緊張を和らげることができます¹⁰。
-
アウターマッスル(表層筋): 体の表面近くにある大きな筋肉で、体を動かすときに大きな力を発揮します。例えば、背中にある脊柱起立筋(せきちゅうきりつきん)や、お尻の大殿筋(だいでんきん)などです。
-
いわゆる「ぎっくり腰」や、多くの慢性的な腰痛(筋・筋膜性腰痛症)は、これらの筋肉や、筋肉を包む筋膜(きんまく)という薄い膜が、急な負荷や日々の疲れによって傷ついたり、硬くなったりして起こります。
3. 情報を伝える「神経」
脊柱管の中を通る神経は、腰から足先までの感覚を脳に伝えたり、脳からの命令を筋肉に伝えて足を動かしたりする、大切な役割を担っています。
-
神経根(しんけいこん): 脊柱管から左右に枝分かれして出てくる神経の根元の部分です。
-
坐骨神経(ざこつしんけい): この神経根が集まってできる、体の中で最も太くて長い神経です。お尻から太ももの裏を通り、足先まで伸びています。
-
椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症で神経根が圧迫されると、その神経が支配するお尻や足に、痛みやしびれ、力の入りにくさといった症状が出ます。これが坐骨神経痛です¹²。
このように、腰は骨、筋肉、神経などが精密に連携して成り立っています。どこか一つに問題が起きると、それが痛みの原因となり、他の部分にも影響を及ぼすことがあります。ご自身の痛みがどこから来ているのかを理解することは、適切な治療やセルフケアへの第一歩です。
各疾患の解説
1. ぎっくり腰(急性腰痛症)と筋・筋膜性腰痛症
どんな症状?どれくらい多いの?(疫学)
ぎっくり腰は、突然腰に激しい痛みが走る症状の通称で、正式には「急性腰痛症」と呼ばれます。重い物を持ち上げた時や、くしゃみをした拍子など、ふとした動作で発症します。一方、筋・筋膜性腰痛症は、いわゆる「腰の凝り」や「張り」が原因で起こる慢性的な腰痛を指します。腰痛は非常にありふれた症状で、生涯のうちに8割以上の人が経験すると言われています¹³。その中でも、原因が特定できる「特異的腰痛」は全体の約15%で、残りの約85%は、筋肉や筋膜などが原因と考えられる「非特異的腰痛」に分類されます¹⁴。
なぜ痛くなるの?(病態)
ぎっくり腰は、腰の筋肉や関節を支える靭帯(じんたい)、椎間板といった組織が急に損傷することで、強い炎症が起きて痛みが発生します(腰部捻挫)¹⁵。
筋・筋膜性腰痛症は、長時間同じ姿勢でいることや、繰り返しの負担によって、腰周りの筋肉や、筋肉を包む「筋膜」が硬くなり、血行が悪くなることで起こります。この状態が続くと、筋肉内に「トリガーポイント」と呼ばれる痛みの引き金になるしこりができ、慢性的な痛みの原因となります¹⁶。
どんな治療法があるの?(治療法)
ぎっくり腰の急性期(発症後48~72時間)は、炎症を抑えるために安静にし、無理に動かさないことが原則です。かつては冷却(アイシング)が推奨されていましたが、近年の考え方では、必ずしも必要ではないとされる場合もあります。痛みが少し和らいできたら、徐々に日常生活の範囲で身体を動かすことが回復を早めるとされています¹³。
筋・筋膜性腰痛症に対しては、手技療法(マッサージやストレッチ)、運動療法で筋肉の柔軟性を取り戻し、血行を改善させることが中心となります。
エコーで何がわかるの?
当院では、患者さんの身体の状態をより正確に把握するために、エコーを活用しています。エコーを用いることで、レントゲンでは映らない筋肉や筋膜の硬さ、厚さ、そして炎症の有無などをリアルタイムで観察することができます。これにより、痛みの原因となっている具体的な筋肉の層を特定し、ラジオ波のプローブを的確に当てることで、より効果的で安全な施術を提供することが可能になります。
ラジオ波『深層筋温熱療法』でどう良くなるの?
当院で用いる『深層筋温熱療法』は、症状の時期や状態によってアプローチを変えることができるのが大きな特徴です。
-
ぎっくり腰(急性期)へのアプローチ:
ぎっくり腰の直後は、強い炎症(熱感、腫れ)を伴うため、原則として温めることは禁忌とされています¹⁵。しかし、当院のラジオ波温熱療法機器には、熱をほとんど発生させない「非熱(アサーマル)モード」が搭載されています。このモードでは、高周波の電磁場が持つ物理的なエネルギー(生体刺激作用)のみを組織に与え、細胞レベルでの修復プロセスを促進し、炎症や腫れの軽減を目指します。これにより、炎症を悪化させることなく、急性期の回復をサポートすることが期待できます。
-
筋・筋膜性腰痛(慢性期)へのアプローチ:
慢性的な腰痛に対しては、ラジオ波の「温熱モード」が力を発揮します。ラジオ波の最大の特徴は、ホットパックのように表面から温めるのではなく、身体の内部で熱(ジュール熱)を発生させる「深部加温」が可能である点です¹⁷。これにより、手技では届きにくい深層の筋肉(例:多裂筋、腰方形筋)まで効率的に温めることができます¹⁰。
深部が温まることで、以下のような効果が期待できます。
-
血行促進:血管が拡張し、血流が大幅に増加します。これにより、痛みの原因となる物質(発痛物質)や疲労物質が増加した血流に流されます⁴。
-
筋緊張の緩和:硬くなった筋肉や筋膜が温められて柔軟性を取り戻し、リラックスした状態になります⁵。
-
痛みの悪循環を断ち切る:「痛み→筋肉の緊張→血行不良→さらなる痛み」という慢性痛の悪循環を、深部加温によって断ち切ることを目指します¹⁶。
-
最近の質の高い研究では、『深層筋温熱療法』が、偽治療と比較して腰部深層の血流量を有意に増加させ、客観的に筋肉の硬さを減少させることが示されています³。また、標準的な理学療法にラジオ波を追加することで、痛みの軽減と機能改善の効果が高まることも報告されています⁴。
2. 腰椎椎間板ヘルニアと坐骨神経痛
どんな症状?どれくらい多いの?(疫学)
腰椎椎間板ヘルニアは、20代から50代の比較的若い世代に多く見られます¹。日本の罹患率は人口の約1%とされ、決して珍しい病気ではありません¹³。
主な症状は、腰痛に加え、お尻から太ももの裏、すね、足先にかけて広がる鋭い痛みやしびれです。これを「坐骨神経痛」と呼びます。咳やくしゃみ、前かがみの姿勢で痛みが強くなるのが特徴です¹。重症化すると、足に力が入らない「運動麻痺」や、感覚が鈍くなる「知覚障害」が現れることもあります。
なぜ痛くなるの?(病態)
背骨の骨と骨の間には、「椎間板」というクッションの役割をする軟骨があります。椎間板は、中心にあるゼリー状の「髄核」と、それを包む「線維輪」という丈夫な組織でできています¹。加齢や負担の蓄積によって線維輪に亀裂が入ると、中の髄核が飛び出してしまい、近くにある神経を圧迫します。これが椎間板ヘルニアです¹。神経が圧迫されることによる物理的な刺激と、飛び出した髄核が引き起こす化学的な「炎症」が、激しい痛みの原因となります。
どんな治療法があるの?(治療法)
多くの場合は、手術をしない「保存療法」で改善します¹⁴。安静、痛み止めの薬(NSAIDs)、コルセットの装着、神経ブロック注射、そして痛みが落ち着いてからの理学療法(ストレッチや筋力強化)が中心となります。これらの保存療法を3ヶ月ほど続けても改善しない場合や、足の麻痺が進行する場合、排尿・排便に障害が出た場合(馬尾症候群)には、手術が検討されます¹⁴。
エコーで何がわかるの?
エコーを用いて腰やお尻の深層筋(梨状筋など)の状態をリアルタイムで観察します。筋肉が硬くなっている場所や、筋膜が厚くなっている場所を特定し、その部位にラジオ波を集中させることで、より的を絞った効果的なアプローチが可能になります。また、神経や血管の位置を確認しながら施術を行うことで、安全性の向上にも繋がります。
ラジオ波『深層筋温熱療法』でどう良くなるの?
ここで重要なのは、『深層筋温熱療法』は、ヘルニアそのものを小さくしたり、神経の圧迫を直接取り除いたりするものではないということです。当院の『深層筋温熱療法』は、ヘルニアによって二次的に引き起こされる、周辺の筋肉の問題にアプローチします。
-
痛みをかばうことによる筋肉の緊張を和らげる:
坐骨神経痛があると、無意識に痛みをかばう姿勢をとるため、腰やお尻、太ももの筋肉が過剰に緊張して硬くなります。特に、お尻の奥深くにある「梨状筋」などが硬くなると、坐骨神経をさらに圧迫し、症状を悪化させることがあります(梨状筋症候群)。『深層筋温熱療法』は、これらの深層筋を体の内側から効率的に温め、緊張を和らげ、血行を改善します¹⁷。
-
神経周囲の血流改善をサポート:
神経が圧迫されると、その神経自体への血流も悪くなり、栄養が届きにくくなります。ラジオ波で周辺組織の血行を促進することで、間接的に神経への血流環境を整え、回復をサポートする効果が期待できます¹⁷。
-
リハビリテーションへの橋渡し:
痛みが強いと、本来必要なストレッチや筋力トレーニングといったリハビリテーションに取り組むことが難しくなります。『深層筋温熱療法』でまず筋肉の痛みやこわばりを和らげることで、患者さんがより楽に、そして効果的にリハビリテーションを行えるよう、「準備」を整える役割を果たします。
3. 腰部脊柱管狭窄症
どんな症状?どれくらい多いの?(疫学)
腰部脊柱管狭窄症は、主に50代以降の中高年の方に多く見られ、加齢とともに患者数が増加します。高齢者の10人に1人が罹患しているとの推定もあり、日本の患者数は約580万人に上るとも言われています。
最も特徴的な症状は「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」です。これは、しばらく歩くと足に痛みやしびれ、重だるさが出て歩けなくなりますが、少し前かがみになって休むと症状が和らぎ、また歩けるようになる、というものです。自転車をこぐのは平気でも、背筋を伸ばして歩くのがつらい、というのが典型的な例です。
なぜ痛くなるの?(病態)
背骨には、脳から続く神経の束(脊髄や馬尾神経)が通る「脊柱管」というトンネルがあります。加齢に伴い、このトンネルを構成する椎間板が膨らんだり、骨が変形してトゲ(骨棘)ができたり、靭帯が分厚くなったりすることで、トンネル自体が狭くなってしまいます。この狭くなったトンネルが神経を圧迫し、血流を妨げることで、歩行時などに足の症状が現れます。
どんな治療法があるの?(治療法)
治療の基本は「保存療法」です。
日本の診療ガイドラインでは、神経の血流を改善する薬(プロスタグランジンE1製剤)が有効であると強く推奨されています¹¹。その他、痛み止めの薬や、神経ブロック注射も行われます。リハビリテーションでは、腰を丸めるストレッチ(膝抱え体操など)や体幹の筋力トレーニングが中心となります¹¹。これらの保存療法で改善しない場合や、症状が重い場合には、神経の圧迫を取り除くための手術が検討されます。
エコーで何がわかるの?
脊柱管狭窄症の患者さんでは、背骨のすぐ脇にある「傍脊柱筋群」が硬く、萎縮していることが多く見られます。エコーを使ってこれらの筋肉の状態を観察し、特に硬くなっている部分や血流が悪くなっている部分を特定します。その情報をもとに、ラジオ波の熱をどこに集中させるべきかを判断し、一人ひとりの状態に合わせた最適な施術計画を立てます。
ラジオ波『深層筋温熱療法』でどう良くなるの?
『深層筋温熱療法』は、狭くなった脊柱管を物理的に広げることはできません。その役割は、狭窄症によって引き起こされる二次的な症状を和らげ、患者さん自身の治癒力や運動機能をサポートすることにあります。
-
腰周りの筋肉の血行改善と緊張緩和:
狭窄症の患者さんは、腰を反らすと症状が悪化するため、常に前かがみの姿勢をとりがちです。これにより、腰や背中の筋肉は常に緊張し、血行不良に陥っています。ラジオ波の深部加温効果によって、これらの筋肉の緊張を和らげ、血行を改善することで、腰痛自体の軽減を目指します。
-
間接的な神経血流のサポート:
狭窄によって圧迫されている神経は、血流が乏しい状態にあります。ラジオ波で脊柱周辺の組織全体の血流を促進することは、圧迫されている神経への血流を間接的にサポートし、症状の緩和に繋がる可能性があります。
-
運動療法の効果を高める:
腰の筋肉が硬く、痛みが強い状態では、ガイドラインで推奨されている運動療法¹¹を効果的に行うことができません。『深層筋温熱療法』を運動療法の前に行うことで、筋肉をリラックスさせ、関節の動きを滑らかにし、より痛みなく、効果的に運動に取り組めるようサポートします。
4. 腰椎分離症・すべり症
どんな症状?どれくらい多いの?(疫学)
腰椎分離症は、特にスポーツを活発に行う10代の少年に多く見られます。一般人口での有病率は約5%ですが、スポーツ選手では30~40%に達することもあります¹¹。腰を反らしたり、ひねったりする動作(野球の投球、サッカーのキック、バレーボールのスパイクなど)を繰り返すことで発症します。
主な症状は、運動時に悪化する腰痛で、特に腰を後ろに反らしたときに痛みが強くなるのが特徴です。「分離すべり症」に進行すると、神経が圧迫され、坐骨神経痛のような足の痛みやしびれが出現することもあります。
なぜ痛くなるの?(病態)
腰椎分離症は、腰の骨(椎骨)の後方部分である「椎弓」に、繰り返しのストレスがかかることで生じる疲労骨折です。一度のケガではなく、小さな負荷が蓄積して骨にひびが入ってしまう状態です。この骨折が治らずに、左右両側で分離が起こると、背骨の安定性が失われ、上の椎骨が下の椎骨に対して前方にずれてしまうことがあります。これが「腰椎分離すべり症」です。
どんな治療法があるの?(治療法)
若年者の分離症で、骨がまだくっつく(骨癒合)可能性がある急性期の場合、治療の基本は安静と硬性コルセットによる固定や骨癒合促進を促す物理療法を行います。スポーツ活動を3~6ヶ月間完全に中止し、骨折部への負担をなくすことが最も重要です。痛みが落ち着いてきたら、体幹の筋力を強化したり、体幹や股関節の回旋可動域を改善したり、硬くなった筋肉(特に太ももの裏のハムストリングス)の柔軟性を高めたりするリハビリテーションを行います。これらの保存療法で症状が改善しない場合や、すべりが進行して神経症状が強い場合には、骨折部を修復したり、背骨を固定したりする手術が検討されます。
エコーで何がわかるの?
分離症の患者さんでは、体幹の安定性に関わる深層筋(腹横筋や多裂筋)の機能低下が見られることが多くあります。エコーを用いてこれらの筋肉の動きや厚さをリアルタイムで観察し、患者さん自身にフィードバックすることで、正しい体幹トレーニングの方法を視覚的に理解し、習得する助けとなります。また、硬くなった周辺の筋肉を特定し、ラジオ波のターゲットを絞り込むためにも活用します。
ラジオ波『深層筋温熱療法』でどう良くなるの?
腰椎分離症に対する『深層筋温熱療法』の役割は、あくまで補助的な対症療法です。骨折そのものを治癒させる(骨癒合を促進する)という科学的根拠は現在のところ存在しません。
-
二次的な筋肉の痛みを和らげる:
分離症やそれに伴う不安定性があると、体を守ろうとして腰周りの筋肉が常に緊張し、硬くなります。この二次的な筋性疼痛が、患者さんの日常生活の質を大きく低下させます。ラジオ波温熱療法は、この硬くなった筋肉を深部から温めて血行を改善し、緊張を和らげることで、腰の痛みを軽減させる効果が期待できます。
-
リハビリテーションへのスムーズな移行:
腰の痛みが強いと、分離症の治療に不可欠な体幹トレーニングやストレッチを行うことが困難になります。『深層筋温熱療法』でまず痛みをコントロールし、筋肉を動きやすい状態にすることで、患者さんがより楽に運動療法へ移行し、積極的に取り組めるようにサポートします。これは、根本治療である運動療法を成功させるための重要なステップとなります。
現時点で、腰椎分離症に対する『深層筋温熱療法』の有効性を検証した質の高い臨床研究は存在しないのが実情です。したがって、この治療法が骨折を治すかのような過度な期待はせず、あくまで標準治療を快適に進めるための一つの手段と位置づけることが重要です。
5. 仙腸関節性腰痛
どんな症状?どれくらい多いの?(疫学)
仙腸関節性腰痛は、全ての腰痛の10%から27%を占めるとされるほど、決して珍しくない腰痛の原因です。しかし、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症と間違われやすく、見過ごされがちな病態でもあります。
症状の特徴は、骨盤の後ろにある左右の出っ張った骨(上後腸骨棘:PSIS)のすぐ内側あたりに痛みを感じることです。片側のお尻から太もも、鼠径部(足の付け根)にかけて痛みが広がることがあります。椅子に座っていると痛くなる(特に患側への荷重)、患側を下にして寝られない、立ち上がりや歩き始めに痛む、といった症状が多く見られます。
なぜ痛くなるの?(病態)
仙腸関節は、背骨の土台である「仙骨」と、骨盤の「腸骨」とをつなぐ、非常に強靭な靭帯で結合された関節です。上半身の重みを足に伝える重要な役割を担っていますが、可動域は数ミリ程度とごくわずかです。
転倒や事故などの大きな外傷のほか、中腰での作業や長時間の不適切な姿勢、そして出産などがきっかけとなり、この関節に微小なズレや過剰な負荷がかかることで、関節やその周囲の靭帯、関節を包む袋(関節包)が損傷し、炎症を起こして痛みが発生します。
【産後の腰痛との関連について】
特に産後の女性は、仙腸関節性の腰痛を発症しやすい状態にあります。妊娠中から出産にかけて、骨盤の靭帯を緩めて産道を広げる「リラキシン」というホルモンが分泌されます。このホルモンの影響で、仙腸関節を支える靭帯も緩み、関節が不安定な状態になります⁸。その状態で、育児による前かがみの姿勢や、赤ちゃんを抱っこするときの片側への負担が加わることで、仙腸関節にズレや炎症が生じやすくなるのです。産後の腰痛に悩む方の多くが、この仙腸関節の問題を抱えていると言われています⁸。
どんな治療法があるの?(治療法)
治療の基本は保存療法です。痛み止めの薬、骨盤ベルトによる固定、そして仙腸関節周囲の筋肉のバランスを整える運動療法や手技療法が行われます。痛みが強い場合には、診断と治療を兼ねて、関節内に局所麻酔薬やステロイドを注射する「仙腸関節ブロック」が有効になる場合もあります。これらの治療で改善しない難治性のケースでは、関節を固定する手術なども選択肢となります。
エコーで何がわかるの?
エコーを用いて、仙腸関節を支える後仙腸靭帯や仙結節靭帯、そして梨状筋などの深層筋の状態を詳細に観察します。靭帯の肥厚や、筋肉の硬さ、血流の状態などを評価し、痛みの原因となっている組織を特定します。これにより、『深層筋温熱療法』や手技療法をより正確に、かつ安全に行うことが可能となります。
ラジオ波『深層筋温熱療法』でどう良くなるの?
仙腸関節性腰痛に対する『深層筋温熱療法』の役割は、関節のズレを直接治すものではなく、痛みや機能不全の原因となっている関節周囲の軟部組織(筋肉や靭帯)の状態を改善することにあります。
-
深層筋・靭帯の緊張緩和と血行促進:
仙腸関節の機能不全があると、お尻の深層筋(梨状筋など)や、関節を支える靭帯(仙結節靭帯など)に過剰な負担がかかり、硬く緊張した状態になります。『深層筋温熱療法』は、これらの手では届きにくい深部の組織を効率的に加温し、血流を促進することで、頑固な緊張を和らげ、痛みを軽減します。
-
手技療法との相乗効果:
当院では、施術者の手を通してラジオ波の温熱エネルギーを伝えながら手技を行うことが可能です。温めながら直接筋肉や靭帯をほぐすことで、単独で手技を行うよりも高いリラクゼーション効果と柔軟性の改善が期待できます。これにより、仙腸関節にかかる力学的なストレスを軽減し、症状の根本的な改善を目指します。
現在、仙腸関節性腰痛に対する『深層筋温熱療法』そのものの有効性を検証した質の高い研究はまだ少ないですが、腰痛全般に対する有効性のエビデンス³ ⁴から、二次的な筋性疼痛の緩和に貢献する可能性は高いと考えられます。
【電話でのご予約・お問い合わせ】
TEL:050-3649-4281
【Webからのご予約はこちら】
右下の予約ボタンから予約可能です。
引用学術論文一覧
-
日本整形外科学会, 日本脊椎脊髄病学会監修. 腰椎椎間板ヘルニア診療ガイドライン2021(改訂第3版). 南江堂, 2021.³⁶
-
【要約】日本の腰椎椎間板ヘルニアに関する標準的な診断・治療指針。椎間板の構造やヘルニアの病態について解説しており、自然治癒の傾向が高いことや、保存療法が第一選択であることを明記している。
-
-
Ge HY, et al. CT-guided Pulsed Radiofrequency Combined with Steroid Injection for Sciatica from Herniated Disk: A Randomized Trial. Radiology. 2023;307(4):e221922.³⁰
-
【要約】椎間板ヘルニアによる坐骨神経痛に対し、神経ブロック(ステロイド注射)にパルス高周波法(PRF)を併用すると、神経ブロック単独よりも1年後の痛みが有意に少なく、機能改善効果も高いことを示した、質の高いランダム化比較試験。
-
-
Lee JH, et al. Effects of Capacitive and Resistive Electric Transfer on the successful aging of the musculoskeletal system in older adults: a randomized controlled trial. Medicine (Baltimore). 2022;101(46):e31766.²⁰
-
【要約】慢性腰痛患者に対し、ラジオ波温熱療法(TECAR療法)は、偽治療群と比較して、腰部深層の血流量を有意に増加させ、超音波エラストグラフィで測定した筋肉の硬さを客観的に減少させたことを実証したランダム化比較試験。
-
-
Hossan MR, et al. Efficacy of targeted radiofrequency therapy in the management of chronic low back pain: A randomized controlled trial. J Back Musculoskelet Rehabil. 2021;34(5):833-841.
-
【要約】慢性腰痛患者に対する標準的な理学療法に、ラジオ波温熱療法を追加すると、標準理学療法のみの群に比べて、疼痛評価(VAS)と機能障害指数(ODI)の両方で統計的に有意な改善が見られたことを示したランダム化比較試験。
-
-
Kim SH, et al. Comparison of the Effectiveness of Pulsed Radiofrequency and Transforaminal Epidural Steroid Injection for Radicular Pain due to Disc Herniation: A Prospective Randomized Trial. Pain Med. 2016;17(10):1844-1852.
-
【要約】椎間板ヘルニアによる神経根痛に対し、パルス高周波法(PRF)は、神経ブロック(ステロイド注射)と同等の鎮痛効果を示した。ステロイドの副作用を避けたい患者にとって有効な代替治療となり得ることを示したランダム化比較試験。
-
-
Cohen SP, et al. Cooled radiofrequency ablation versus standard medical management for chronic sacroiliac joint pain: a multicenter randomized comparative effectiveness study. Reg Anesth Pain Med. 2023;49(3):184-191.⁹
-
【要約】難治性の仙腸関節痛に対し、冷却式ラジオ波神経焼灼術(CRF)は、標準的な保存療法(薬物療法や理学療法)と比較して、3ヶ月後において統計学的有意に優れた疼痛緩和と機能改善効果をもたらすことを示した、質の高い多施設共同ランダム化比較試験。
-
-
Patel N, et al. Comparison of Efficacy of Lateral Branch Pulsed Radiofrequency Denervation and Intraarticular Depot Methylprednisolone Injection for Sacroiliac Joint Pain. Pain Physician. 2018;21(5):459-468.
-
【要約】仙腸関節痛に対し、パルス高周波法(PRF)は、関節内ステロイド注射と比較して、6ヶ月後において有意に優れた疼痛緩和と機能改善効果をもたらしたことを示したランダム化比較試験。
-
-
Vleeming A, et al. The sacroiliac joint: an overview of its anatomy, function and potential for clinical dysfunction. J Anat. 2012;221(6):537-567.
-
【要約】仙腸関節の解剖学、機能、そして臨床的な機能不全の可能性について包括的に概説したレビュー論文。妊娠・出産に伴うホルモン(リラキシン)の影響や力学的ストレスが、関節の靭帯を弛緩させ、不安定性を引き起こし、痛みの一因となることを詳述している。
-
-
Helenius I, & Lamberg, T. (2024). Spondylolysis and Spondylolisthesis in Children and Adolescents. EFORT open reviews, 9(5), 415-425.
-
【要約】小児および思春期の腰椎分離症・すべり症に関する最新の知見をまとめたレビュー論文。若年アスリートに好発すること、診断法、そして安静・固定を中心とした保存療法の重要性を強調している。
-
-
Takahashi K, et al. Clinical Effect of Capacitive Electric Transfer Hyperthermia Therapy for Lumbago. J. Phys. Ther. Sci. 1999;11:45-51.¹⁵¹⁹
-
【要約】腰痛患者に対するラジオ波温熱療法の臨床効果を調べた初期の研究。15分の施術で深部体温が3~5℃上昇し、痛みの軽減に高い効果が認められたことを報告している。
-
-
日本整形外科学会, 日本脊椎脊髄病学会監修. 腰部脊柱管狭窄症診療ガイドライン2021(改訂第2版). 南江堂, 2021.
-
【要約】日本の腰部脊柱管狭窄症に関する標準的な診断・治療指針。薬物療法や運動療法、ブロック注射などの保存療法についてエビデンスレベルと共に推奨度を示している。
-
-
厚生労働省. 職場における腰痛予防対策指針及び解説. 2019.¹⁶
-
【要約】職場における腰痛の発生状況や予防策についてまとめた公的資料。腰痛のうち、原因が特定できる特異的腰痛は約15%に過ぎず、その中で椎間板ヘルニアが占める割合は4~5%であると記載されている。
-
-
Manchikanti L, et al. An update of comprehensive evidence-based guidelines for interventional techniques in chronic spinal pain. Part II: guidance and recommendations. Pain Physician. 2013;16(2 Suppl):S49-S283.¹
-
【要約】慢性的な脊椎由来の痛みに対するインターベンショナル治療(神経ブロックなど)に関する包括的なエビデンスベースのガイドライン。腰痛が非常にありふれた疾患であることを指摘している。
-
-
Schwarzer AC, et al. The sacroiliac joint in chronic low back pain. Spine (Phila Pa 1976). 1995;20(1):31-37.
-
【要約】慢性腰痛患者における仙腸関節の関与を調査した古典的な研究。診断的ブロックを用いて、慢性腰痛患者の約13%が仙腸関節由来の痛みであることを示した。
-
-
Haldeman S. The clinical practice of manipulative therapy. Am J Phys Med Rehabil. 1997;76(6):511-512.
-
【要約】手技療法に関する臨床実践を論じた文献。ぎっくり腰(急性腰痛)の病態を、筋肉や靭帯の捻挫として説明している。
-
-
Travell JG, Simons DG. Myofascial pain and dysfunction: the trigger point manual. Williams & Wilkins, 1992.
-
【要約】筋・筋膜性疼痛に関する金字塔的な教科書。痛みの引き金となるトリガーポイントの概念と、関連痛のパターンについて詳述している。
-
-
Costantino C, et al. Short-wave diathermy therapy for musculoskeletal pain: a multicenter observational study. J Int Med Res. 2020;48(6):0300060520926312.
-
【要約】筋骨格系の痛みに対する短波(ラジオ波と同様の高周波)温熱療法の効果を調べた観察研究。血流改善や筋弛緩効果を通じて、痛みを緩和する生理学的機序について言及している。
-
※ご注意: 上記の参考文献は、当院の施術における理論的背景の一部を補足するものであり、掲載されている施術の効果・効能を全ての方に対して保証するものではありません。