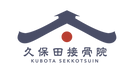
~肩、首、腰の接骨院~
本質と向き合い、健やかな未来を創る
~痛みのメカニズム~
なぜあなたは痛むのか?
痛みの専門家が解き明かす「痛みの正体」
その痛み、なぜ? ~痛みの正体とラジオ波温熱アプローチの科学~
「なぜ、私の痛みだけが長引くのだろう?」
「湿布や薬だけでは、なかなか痛みが取りきれない…」
多くの人が抱える「痛み」の悩み。実はその正体は、単なるケガの信号ではなく、私たちの脳や神経、さらには心のあり方までが複雑に絡み合った、極めて個人的な「体験」です。
このページでは、「痛み」という壮大なテーマを多角的に掘り下げ、なぜ痛みが生まれ、長引き、人によって感じ方が違うのかを4つの章にわたって解き明かします。そして後半の2つの章では、当院が採用する「ラジオ波温熱療法」が、その複雑な痛みのメカニズムに、なぜ科学的根拠を持ってアプローチできるのかを詳しく解説します。
【第1部】痛みの正体を探る
第1章:痛みの基本 ― 体からの危険信号
痛みは、国際疼痛学会(IASP)によって「実際に組織損傷が起きている、あるいは起きる可能性がある状態、あるいはそれに似た、不快な感覚かつ情動体験」と定義されています。これは、痛みが単なる感覚ではなく、「不快だ」「嫌だ」と感じる感情(情動)を伴う体験であることを示しています。
この痛みの旅は、体のあらゆる場所に存在するセンサー「侵害受容器(しんがいじゅようき)」が、体に害を及ぼす可能性のある強い刺激(機械的、熱、化学的刺激)を感知することから始まります。このセンサーが興奮すると、その情報が電気信号となって神経を駆け巡ります。
この信号を運ぶ神経線維には、主に2つのタイプがあり、それぞれが異なる質の痛みを伝えます。
-
一次痛(速い痛み):Aδ(デルタ)線維
-
「チクッ!」「アチッ!」と感じる、鋭く、場所がはっきりとわかる痛みです。有髄線維という高速道路のような神経を伝わるため、信号が脳に届くのが速いのが特徴です。危険を瞬時に察知し、体を守るための重要な役割を担っています。
-
-
二次痛(遅い痛み):C線維
-
ケガをした後に続く「ジンジン」「ズキズキ」とした、鈍く、広範囲に感じる痛みです。無髄線維という一般道のような神経をゆっくり伝わります。この痛みが続くことで、私たちは患部を安静に保ち、回復を促すことができます。
-
第2章:痛みの伝達経路 ― 脊髄の門番と脳への道のり
侵害受容器から発せられた痛みの信号は、脊髄(せきずい)へと到達します。しかし、信号はそのまま脳へ素通りするわけではありません。脊髄の後角という場所で、最初の情報処理が行われます。
ここで重要なのが、1965年に提唱された「ゲートコントロールセオリー」です。
この理論は、脊髄に痛みの信号を脳へ送るか否かを決める「門(ゲート)」のような仕組みが存在すると説明しています。
-
ゲートが開く:Aδ線維やC線維からの痛みの信号が優勢なとき、ゲートは開いて信号を脳へ送ります。
-
ゲートが閉じる:一方で、痛いところを優しくさすると、触覚や圧覚といった心地よい感覚を伝える太い神経線維(Aβ線維)が活性化します。この信号がゲートを閉じる方向に働き、脳へ伝わる痛みの信号を減少させます。
これが、私たちが打撲した場所を思わず手でさすると、痛みが和らぐ科学的な理由です。
ゲートを通過した信号は、脊髄視床路という上り坂を駆け上がり、脳の様々な領域へと送られます。重要なのは、脳には「痛みセンター」のような単一の場所は存在しないという点です。痛みの体験は、複数の脳領域が連携して作り出す、多次元的な産物なのです。
-
感覚的な側面:「どこが、どれくらい、どんなふうに痛いのか」を分析(体性感覚野)。
-
情動的な側面:「不快だ」「つらい」といった感情を生み出す(帯状回、島皮質)。
-
認知的な側面:痛みへの注意、過去の経験との照らし合わせ、痛みの意味づけを行う(前頭前野)。
第3章:痛みの個人差 ― なぜ感じ方が人それぞれ違うのか?
同じケガでも、痛みの感じ方が人によって全く違うのはなぜでしょうか。その答えは、痛みが脳によって能動的に構築される体験であることに由来します。その個人差を生む要因をまとめたのが「生物心理社会モデル」です。
-
生物学的要因(からだ):遺伝子とホルモンが設計する「痛みの感じやすさ」
-
遺伝子と「痛みの閾値」:痛みを感じ始める刺激の強さを「閾値(いきち)」と言います。この「痛みのスイッチの入りやすさ」には、生まれつき個人差があることが科学的に証明されています。研究によれば、痛みの感じやすさの個人差の最大55%は遺伝的要因によって説明できるとされています。例えば、COMT遺伝子という、ストレス物質を分解する酵素の設計図となる遺伝子があります。この遺伝子のタイプによって酵素の働きが異なり、分解能力が低いタイプを持つ人は、ストレス下で痛みを強く感じやすい傾向があることが報告されています。
-
「女性は痛みに強い」は本当か?:よく「女性は出産に耐えるから痛みに強い」と言われます。しかし、科学的な実験(熱や圧迫による実験痛)では、むしろ多くの場面で女性の方が男性よりも痛みに敏感である(閾値が低い)という結果が報告されています。このギャップは、女性ホルモン(エストロゲンなど)の周期的変動が痛みの感受性に影響を与えることや、痛みの伝達に関わる遺伝子の働きに性差があることなどが一因と考えられています。
-
-
心理学的要因(こころ)
-
思考の癖と痛み:「もうこの痛みは治らないかもしれない」といった否定的な考え(破局的思考)は、脳の痛み関連領域を過剰に活動させ、痛みを何倍にも増幅させてしまいます。
-
不安と抑うつ:不安や気分の落ち込みは、脳の痛み抑制システムの働きを弱め、痛みのゲートを開きやすくしてしまいます。
-
過去の経験:過去のつらい痛みの記憶は、新たな痛みに対して過敏に反応させてしまうことがあります。
-
-
社会的要因(かんきょう)
-
職場や家庭でのストレス、社会的な孤立、文化的な背景なども、痛みの感じ方や報告のしやすさに影響を与えます。信頼できる家族や友人のサポートは、痛みを乗り越える上で大きな力となります。
-
つまり、「女性が痛みに強い(あるいは弱い)」と一概に言うことはできず、痛みの種類、ホルモン状態、遺伝的背景、そして心理社会的な文脈が複雑に絡み合った結果、一人ひとり異なる「痛みのモザイク」が形成されているのです。
はい、承知いたしました。 久保田接骨院様のホームページに掲載する「からだの学校」のコンテンツとして、「痛み」をテーマにしたページの原稿を作成します。ご提示いただいた既存の文章とInstagramの投稿内容を統合し、柔道整復師法(広告の制限)を遵守しながら、科学的根拠に基づいた分かりやすい内容に仕上げます。
第4章:なぜ痛みは“ぶり返す”のか? ― 満杯の「コップの水」と神経の警報システム
「しっかり休んだはずなのに、朝から身体が痛い…」 「施術を受けた直後は楽になるのに、しばらくするとすぐに元通りになってしまう…」
このような経験はありませんか?その「繰り返す痛み」は、単なる気のせいではなく、あなたの心と身体が発している重要なメッセージかもしれません。なぜ、一度良くなったはずの痛みが何度もぶり返してしまうのでしょうか。その答えを、私たちの心と体にある「見えないコップ」を例えに、科学的な視点から解き明かしていきます。
あなたの心と体にある「見えないコップ」
私たちの心と体には、それぞれ「見えないコップ」があると想像してみてください。このコップには、日々の様々な負担が「水」として少しずつ溜まっていきます¹⁹³。そして、痛みの正体とは、このコップから水が溢れ出してしまった状態なのです。
コップから水が溢れないようにするためには、「注がれる水の量」を減らすか、「コップから抜く水の量」を増やすかのどちらか、あるいは両方が必要です。このバランスが、痛みのない健やかな毎日を送るための鍵となります。
蛇口から注がれる「消耗」と科学的根拠「アロスタティック負荷」
コップに水を注ぎ続ける蛇口、それは日々の生活における「消耗」です。
-
精神的なストレス
-
睡眠不足
-
栄養の偏り
-
長時間のデスクワークや過度な運動
これらの負担が知らず知らずのうちに積み重なった状態を、科学的には「アロスタティック負荷」と呼びます。これは、心と身体が様々なストレスに適応しようと頑張り続けた結果、摩耗し、疲弊してしまった状態を指す言葉です。アロスタティック負荷が高い状態が続くと、将来的に痛みを引き起こすリスクが高まることが、大規模な研究でも示されています。
コップの水を抜く「修復」活動
一方で、コップの水を意識的に抜く行動、それが「修復」です。
-
質の良い十分な睡眠
-
バランスの取れた食事
-
心地よいと感じる適度な運動
-
趣味やリラックスできる時間
これらの健康的な生活習慣は、コップの水を効果的に減らしてくれます。そして、接骨院での施術も、一時的にコップの水を汲み出すための、非常に大切な「修復」活動の一つなのです。
蛇口から注がれる「消耗」の量が、「修復」によって抜かれる水の量を上回り続ける限り、コップの水は溢れ、痛みは何度でも繰り返されてしまいます。
水が溢れ続けると…神経の警報システム「中枢性感作」
では、コップから水が溢れ続けた状態、つまり痛みが長引くと、私たちの身体の中では何が起こるのでしょうか。
急なケガなどによる痛み(急性痛)が3ヶ月以上続くと、「慢性痛」と呼ばれます。この慢性痛の背後には、しばしば「中枢性感作(ちゅうすいせいかんさ)」という深刻な問題が隠れています。
これは、痛みが長期間続いた結果、コップが脆くなってしまうように、脊髄や脳といった中枢神経系そのものが過敏になってしまった状態です。いわば「火災報知器が誤作動を起こし、煙がないのに常に警報が鳴り響いている状態」と例えられます。
警報システムが誤作動するメカニズム
なぜ、このような誤作動が起きてしまうのでしょうか。
痛みの信号が繰り返し神経に送られ続けると、神経細胞にある「NMDA受容体」というスイッチが常にオンの状態になります。これにより、神経細胞はささいな刺激にも過剰に興奮するようになってしまうのです。さらに、普段は神経のサポート役である「グリア細胞」までが活性化し、炎症を引き起こす物質(炎症性サイトカイン)を放出することで、この興奮状態をさらに悪化させ、維持させてしまいます。
この状態になると、もはや痛みはケガをした場所だけの問題ではなく、中枢神経系そのものの機能異常として捉える必要があります。
中枢性感作が引き起こす3つのサイン
中枢性感作が起こると、元のケガが改善しても、以下のような特徴的な症状が現れることがあります。
-
痛覚過敏(Hyperalgesia) 通常なら少し痛いと感じる程度の刺激(例:軽くぶつける)に対して、耐えがたいほどの激痛を感じてしまう状態です。
-
アロディニア(Allodynia) 服が肌にこすれる、うちわで風を送る、軽く触れるなど、本来は全く痛みを伴わないはずの刺激が、痛みとして感じられてしまう状態です。
-
痛みの拡大 痛みが最初に損傷した部位を越えて、全く関係のない手や足、身体の反対側などにまで広がっていく現象です。
「昔に比べて痛みに敏感になった気がする」、「ちょっとしたことでズキっと痛むことが増えた」と感じる場合、それは神経が疲弊しているサインかもしれません。
久保田接骨院のアプローチ:コップの水を減らし、溢れさせないために
絶望する必要はありません。大切なのは、蛇口を完全に閉めることではなく、「修復」が「消耗」を少しでも上回る日を一日でも多く作ることです。あなたの身体は、その小さな変化にきっと応えてくれます。
久保田接骨院では、患者様一人ひとりの「痛みのモザイク」を丁寧に評価し、なぜコップの水が溢れてしまっているのか、その根本原因に目を向けます。
-
「蛇口を少し締める」お手伝い カウンセリングを通じて、日常生活に隠れた「消耗」の原因(生活習慣、身体のクセ、職場環境など)を一緒に見つけ出し、改善のためのアドバイスを行います。
-
「コップの水を積極的に抜く」お手伝い 手技療法に加え、当院が強みとする「ラジオ波温熱療法」を組み合わせることで、効率的に「修復」を促進し、痛みの緩和を目指します。
【第2部】痛みに対するラジオ波の科学
第5章:ラジオ波温熱療法の原理 ― 体の深部から温める力
つらく複雑な痛みに対し、当院が用いるアプローチの一つが「ラジオ波温熱療法」です。これは、高周波数の電磁波を体に流すことで、体の内部から熱を発生させる物理療法です。
ホットパックや赤外線が体の表面しか温められないのに対し、ラジオ波は体の深部、筋肉や関節といったレベルまで熱エネルギーを到達させられるのが最大の特徴です。
この治療法には、主に2つのモードがあり、目的の深さや組織に応じて使い分けます。
-
CET(キャパシティブ)モード
-
電極が絶縁体でコーティングされており、エネルギーが皮膚直下の浅い層に集中します。皮膚や皮下組織、表層の筋肉を素早く温めるのに適しています。
-
-
RET(レジスティブ)モード
-
電極がコーティングされておらず、エネルギーが体深くまで浸透します。特に、骨、腱、関節、そして硬くなった筋肉など、電気抵抗が高い組織に熱が集まるという特性があります。これにより、施術者が意図した深部の硬結部位などを選択的に加温することが可能です。
-
第6章:なぜラジオ波で痛みが和らぐのか? ― ラジオ波の具体的な作用
ラジオ波によって深部で生み出された熱は、痛みを和らげるために、私たちの体に様々な生理学的変化を引き起こします。
-
① 血流の促進と発痛物質の除去
-
組織の温度が上昇すると、血管が著しく拡張し、局所の血流が増加します。血流が増えることで、痛みを引き起こす原因となるブラジキニンやプロスタグランジンといった発痛物質や、溜まっていた代謝老廃物が効率的に洗い流されます。同時に、組織の修復に必要な酸素や栄養素が豊富に供給され、回復プロセスをサポートします。
-
-
② 筋緊張の緩和(筋弛緩)
-
筋肉には、その伸び縮みを監視する「筋紡錘(きんぼうすい)」というセンサーがあります。温熱は、このセンサーの感度を調整しているγ(ガンマ)運動ニューロンという神経の発火頻度を低下させます。これによりセンサーの感度が鈍化し、結果として筋肉を過剰に収縮させるα(アルファ)運動ニューロンの活動が抑制されます。つまり、筋肉の過剰な緊張状態を神経レベルからリセットし、深いリラクゼーションをもたらすのです。
-
-
③ 結合組織の柔軟性向上
-
ケガや長期間の不動により硬くなった関節包、腱、靭帯といった結合組織は、コラーゲン線維で構成されています。温熱は、このコラーゲンの粘弾性を高め、組織の伸展性を向上させる効果があります。これにより、関節の可動域が改善し、動かしたときの痛みの軽減や、機能回復が期待できます。
-
-
④ 痛みのゲートを閉じ、脳からの抑制を促す
-
ラジオ波による心地よい温熱刺激は、第2章で解説したゲートコントロールセオリーにおける「太い神経線維(Aβ線維)」を活性化させます。これにより、痛みを伝える細い神経線維からの信号を脊髄レベルでブロックし、痛みのゲートを閉じる効果が期待できます。さらに、非侵害的な温熱刺激は、脳から投射される内因性の痛み抑制システム(下降性疼痛抑制系)を賦活する可能性も示唆されており、体自身が持つ痛みと戦う力を高める手助けをします。
-
これらの作用が複合的に働くことで、ラジオ波温熱療法は、急性の痛みから、筋肉の過緊張や関節の硬さを伴う慢性的な痛みまで、幅広い症状の緩和に貢献します。
まとめ
痛みは、単一の原因で説明できるものではなく、「からだ・こころ・かんきょう」が織りなす、あなただけの「モザイク模様」です。だからこそ、その痛みを理解し、適切にアプローチするためには、専門的な知識と評価が不可欠です。ラジオ波温熱療法は、その科学的根拠に基づいた温熱作用により、痛みの悪循環を断ち切り、体の治癒力を引き出す有力な選択肢の一つです。
久保田接骨院では、お一人おひとりの「痛みのモザイク」を丁寧に読み解き、ラジオ波温熱療法と専門的な手技療法を組み合わせた、最適なオーダーメイドの施術をご提案いたします。つらい痛みをあきらめる前に、ぜひ一度、私たちにご相談ください。
【電話でのご予約・お問い合わせ】
TEL:050-3649-4281
【Webからのご予約はこちら】
右下の予約ボタンから予約可能です。
引用学術論文一覧
-
発表年: 1965
演題: Pain Mechanisms: A New Theory
著者: Melzack, R., & Wall, P. D.
学会誌名: Science
要約: 痛みの伝達が脊髄の「門(ゲート)」で調節されるという、画期的な「ゲートコントロールセオリー」を世界で初めて提唱した歴史的な論文。 -
発表年: 1990
演題: Therapeutic heat
著者: Lehmann, J. F., & de Lateur, B. J.
学会誌名: Lehmann, J. F. (Ed.), Therapeutic Heat and Cold
要約: 物理療法における温熱の生理学的効果をまとめた標準的な教科書的文献。血流増加、筋弛緩、結合組織の伸展性向上といったメカニズムを詳細に解説。 -
発表年: 2005
演題: Genetic contributions to pain: a review of findings in humans
著者: Diatchenko, L., et al.
学会誌名: Annual Review of Medicine
要約: COMT遺伝子多型などが痛みの感受性に与える影響をレビューし、遺伝子が痛みの個人差に寄与することを論じた論文。 -
発表年: 2009
演題: Central Sensitization: A Generator of Pain Hypersensitivity by Plasticity of the Central Nervous System
著者: Latremoliere, A., & Woolf, C. J.
学会誌名: Pain
要約: 中枢性感作が、中枢神経系の可塑的な変化によって痛覚過敏を引き起こす分子メカニズムを解説した論文。 -
発表年: 2010
演題: Central sensitization: implications for the diagnosis and treatment of chronic pain
著者: Nijs, J., et al.
学会誌名: Pain
要約: 中枢性感作の臨床的特徴である痛覚過敏(Hyperalgesia)とアロディニア(Allodynia)について解説した論文。 -
発表年: 2012
演題: Human pain and genetics: some basics
著者: Mogil, J. S.
学会誌名: Pain
要約: 痛みの感受性における遺伝的要因と、性別や人種といった社会的要因の相互作用について解説した総説。 -
発表年: 2013
演題: Individual Differences in the Subjective Experience of Pain: New Insights into Mechanisms and Models
著者: Bushnell, M. C., et al.
学会誌名: Nature Reviews Neuroscience
要約: 痛みの主観的体験に関わる脳領域(感覚、情動、認知)と、その個人差を生むメカニズムを解説したトップジャーナル論文。 -
発表年: 2014
演題: Influence of intramuscular heat stimulation on modulation of nociception
著者: Umeda, M., et al.
学会誌名: The Journal of Pain
要約: 非侵害的な温熱刺激が、中枢のオピオイド受容体を介して脳からの痛み抑制システム(下行性疼痛抑制系)を賦活する可能性を示した研究。 -
発表年: 2017
演題: Individual Differences in Pain: Understanding the Mosaic that Makes Pain Personal
著者: Fillingim, R. B.
学会誌名: Pain
要約: 遺伝子、心理、社会要因が複雑に絡み合い、個人に固有の「痛みのモザイク」を形成する生物心理社会モデルを解説。 -
発表年: 2018
演題: General Pathways of Pain Sensation and the Major Descending Modulatory Systems
著者: Chen, J., et al.
学会誌名: International Journal of Molecular Sciences
要約: Aδ線維とC線維による痛みの伝達経路と、脳からの下行性疼痛抑制系についてまとめた総説。 -
発表年: 2023
演題: Central Sensitization and Pain: Pathophysiologic and Clinical Insights
著者: Siracusa, R., et al.
学会誌名: Journal of Clinical Medicine
要約: 国際疼痛学会(IASP)による痛みの定義を紹介し、中枢性感作の病態生理と臨床的特徴を詳述した最新の総説。
※ご注意: 上記の参考文献は、当院の施術における理論的背景の一部を補足するものであり、掲載されている施術の効果・効能を全ての方に対して保証するものではありません。