その「こり」、本当にただの疲れ?筋膜にひそむ痛みのサイン
- 竜祐 久保田
- 8月15日
- 読了時間: 6分
更新日:8月16日

はじめに:繰り返す不調の、その先に
マッサージや整体に定期的に通って、その場では楽になるけれど、気づけばまた同じ肩や腰の重さに悩まされる…。そんな経験はありませんか。
「もう年だから仕方ない」「疲れがたまっているだけ」
そう自分に言い聞かせながらも、心のどこかで「もっと根本的な何かがあるのではないか」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。
もし、あなたが長年付き合ってきたその不調が、レントゲンには映らない「筋膜」のしわざだとしたら。今回は、特に40代以降の女性に多く見られる、単なる「こり」とは少し違う、身体の深層からのサインについて、少しだけ耳を傾けてみませんか。
1. 痛みの震源地「トリガーポイント」とは?
いつも重だるさを感じる部分を指でぐっと押してみると、ひときわ硬く、強い痛みを感じる「しこり」のようなものに触れたことはないでしょうか。
それは「トリガーポイント」と呼ばれ、筋筋膜性疼痛症候群(MPS)という状態の大きな特徴です 。これは、筋肉を包んでいる「筋膜」や筋肉そのものにトラブルが生じ、感覚が過敏になってしまった点のこと。単なる圧痛点と違うのは、そこを押すと、離れた場所にまで痛みが響き渡る「関連痛」という現象を引き起こすことがある点です 。
例えば、肩にあるトリガーポイントが原因で、腕や指先にじんわりとした痛みやしびれのような感覚を覚えたり、腰のトリガーポイントがお尻や脚の不調につながったり。湿布を貼ってもなかなか良くならないと感じるのは、痛みの発生源が、感じている場所とは違うところにあるからかもしれません。
2. なぜ40代の私たちに多いの? 身体の変化という静かな嵐
なぜ、この筋膜のトラブルは40代の女性に起こりやすいのでしょうか。それは、この年代の女性が、身体的にも社会的にも、まるで様々な要因が重なり合う「パーフェクトストーム」の中心にいるからかもしれません 。
ライフスタイルによる負荷
長時間のデスクワークやスマートフォンの使用は、無意識のうちに頭が前に出る「前方頭位姿勢」などを招き、首や肩、背中の筋肉に持続的な負担をかけ続けます 。また、家事や育児といった日々の反復的な動作も、特定の筋肉への微細なダメージの蓄積につながります 。
見過ごされがちなホルモンのゆらぎ
40代は、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌がゆらぎ始める「更年期移行期(ペリメノポーズ)」にあたります 。エストロゲンは、筋肉や骨、そして筋膜のような結合組織のしなやかさを保つ役割も担っています。このホルモンバランスの変化が、これまで何ともなかった身体への負荷に対する脆弱性を高めている可能性があるのです 。
心と身体のつながり
仕事、家庭、親のことなど、多岐にわたる責任を担う40代は、精神的なストレスを感じやすい時期でもあります 。ストレスや不安は、無意識のうちに歯を食いしばらせたり、肩に力が入ったりと、身体を常に緊張状態にさせます。この持続的な緊張が、トリガーポイントを活性化させる引き金になることも少なくありません 。さらに、痛みが気になって眠りが浅くなると、身体の修復が妨げられ、「痛みで眠れない、眠れないから痛みが強くなる」という悪循環に陥ってしまうこともあります 。
これらの要因は、決して別々に存在するのではなく、互いに影響し合い、あなたの不調をより複雑で根深いものにしているのかもしれません。
3. 「見えない痛み」の正体は、筋膜の”よじれ”と”滑りの悪さ”
最近の研究では、筋肉そのものだけでなく、それを包むウェットスーツのような薄い膜、「筋膜」の重要性が注目されています 。筋膜は、身体の隅々までネットワークとして張り巡らされ、筋肉や内臓を正しい位置に保ち、力の伝達を助ける大切な組織です。
しかし、前述のような持続的な負荷やストレスにさらされると、この筋膜が「高密度化」し、厚く硬くなってしまうことがあります 。さらに、筋膜はいくつかの層になって重なっていますが、その層と層の間の滑りが悪くなる「滑走不全」という状態に陥ることも。
これは、本来スムーズに動くはずの組織同士が癒着し、動きを妨げ、痛みやこわばりの原因となるのです 。超音波(エコー)で観察すると、実際に筋膜が肥厚し、白く映る様子が確認されることもあり、これまで「気のせい」や「原因不明」とされてきた痛みが、客観的に捉えられるようになってきています 。
4. 身体の深部を温めるということ
では、このような筋膜のトラブルによって生じる痛みの悪循環を断ち切るには、どうすれば良いのでしょうか。その一つの考え方が、「身体の深部を温める」というアプローチです。
トリガーポイントの周辺では、筋肉が持続的に収縮することで血流が阻害され、酸素や栄養が不足する「エネルギー危機」と呼ばれる状態に陥っていると考えられています 。これがさらなる痛みを呼び、悪循環を生み出すのです。
ここで役立つのが、ラジオ波などを用いて身体の深部に熱を発生させる「深部温熱」という考え方です。お風呂やホットパックのように表面から温めるのとは異なり、高周波のエネルギーが身体の内部で熱に変わることで、5〜10cmといった深層部にある筋膜や筋肉に直接アプローチすることができます 。
深部で組織の温度が上昇すると、血管が拡張して局所の血流が促され、エネルギー危機状態の緩和が期待できます 。また、熱には、筋膜などを構成するコラーゲン線維の柔軟性を高める働きも示唆されており、硬くなった組織の伸展性を助け、滑走不全の改善にもつながる可能性があります 。
おわりに:ご自身の身体と、もう一度向き合うために
長引く不調は、決して気のせいでも、単なる年齢のせいでもありません。それは、これまで頑張ってきたあなたへの、身体からの大切なメッセージです。
その声に耳を傾け、姿勢を少し見直してみる、心安らぐ時間を作る、そして時には専門家の視点を借りてみる。そうした一つひとつの丁寧な積み重ねが、健やかな明日へとつながっていくはずです。
この記事が、ご自身の身体と改めて向き合い、より良い解決策を探すための一助となれば幸いです。
(この投稿は、以下の科学的知見を参考にしています。)
論文1: Fernández-de-Las-Peñas, C., & Dommerholt, J. (2018). "International Consensus on Diagnostic Criteria and Clinical Considerations of Myofascial Trigger Points: A Delphi Study". Pain Medicine.
解説: 筋筋膜性トリガーポイントの診断基準について、国際的な専門家たちが合意形成を行った研究です。触診による3つの必須基準(索状硬結、過敏な圧痛点、関連痛の再現)が示され、診断の客観性を高める上で重要な指針となっています 。
論文2: De la Cruz-Torres, B., et al. (2021). "B-mode ultrasound characterization of myofascial trigger points and their response to physiotherapy interventions: a systematic review". Journal of Invasive Physiotherapy & Manual Medicine.
解説: 筋筋膜トリガーポイントを超音波画像でどのように捉えるか、そして物理療法によってどう変化するかを調査した複数の研究をまとめたシステマティックレビューです。「見えない痛み」を客観的に可視化する超音波評価の有用性を示しています 。
論文3: Geri, T., et al. (2023). "Effects of Transfer Energy Capacitive and Resistive On Musculoskeletal Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis". Global Medical Journal.
解説: ラジオ波温熱療法(CRET/TECAR)が筋骨格系の痛みにどのような効果をもたらすかについて、複数の質の高い研究を統合・分析したメタアナリシスです。この療法が疼痛軽減に有意な効果をもたらすことを示唆しており、温熱アプローチの科学的根拠の一つとなっています 。
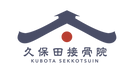



コメント