その不調、ホルモンの「量」だけが理由じゃないかも?大豆イソフラボンの賢い働き
- 竜祐 久保田
- 8月15日
- 読了時間: 7分

ゆらぎの季節を、しなやかに。大豆の恵みが教えてくれる、私たちの身体との新しい対話
年齢を重ねる中で、ふと訪れる心と身体の変化。それは、穏やかだった湖面に小石が投げ込まれたように、静かな波紋を広げます。
「以前とは違うな…」と感じるそのゆらぎの正体を探して、私たちは様々な情報をめぐります。巷には多くの健康法やサプリメントの情報が溢れ、その多さに少しだけ心が疲れてしまう日もあるかもしれません。特に「女性ホルモンを補う」という言葉は、まるで魔法のように聞こえる一方で、本当に自分にとって最善の方法なのだろうか、と立ち止まって考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
もし、そのゆらぎとの向き合い方が、「減っていくものを、ただ外から補う」という足し算の発想だけではないとしたら。
今日は、古くから私たちの食生活に寄り添ってきた「大豆」の恵み、イソフラボンについて、少し視点を変えたお話をしてみたいと思います。それは、私たちの身体が本来持っている「応答する力」に、そっと耳を傾けるような、新しい対話の始まりかもしれません。
本当は「増やして」いなかった?イソフラボンの意外な真実
多くの方が、「大豆イソフラボンは、体内で女性ホルモン(エストロゲン)のように働く。だから、減ってしまったホルモンを増やしてくれる」というイメージをお持ちかもしれません。しかし、近年の非常に信頼性の高い科学的研究は、少し違う景色を見せてくれています。
実は、大豆イソフラボンを摂取しても、体内でつくられる女性ホルモンの量が「増える」ことはない、ということが分かってきたのです。2024年に行われた、40もの研究結果を統合した分析でも、イソフラボンを摂取したグループとそうでないグループとで、血中の女性ホルモンの量に意味のある違いは見られない、と結論づけられています。
身体の中のホルモン量が変わらないのに、なぜホットフラッシュのような不調が和らいだり、気持ちが穏やかになったりといった変化が語られるのでしょうか。その不思議を解き明かす鍵は、「量」ではなく「働き方」にありました。イソフラボンは、私たちの身体の中で、実に賢く、そして繊細な「調整役」として機能していたのです。
身体に備わる二つの「スイッチ」と、賢いメッセンジャー
私たちの身体の細胞には、女性ホルモンを受け取るための「鍵穴」のようなものが存在します。これを「エストロゲン受容体」と呼びます。そして、この鍵穴には、実は性質の異なる2つのタイプがあることが知られています。
α(アルファ)受容体(ERα): 主に乳腺や子宮などに多く、細胞の「増殖」に関わるスイッチです。
β(ベータ)受容体(ERβ): 主に骨や脳、血管、泌尿生殖器などに多く、細胞の増殖を「抑制」したり、機能を「分化・成熟」させたりすることに関わる、穏やかなスイッチです。
女性ホルモンは、この両方のスイッチをパワフルに押すことができます。一方で、大豆イソフラボンは、まるで心得たメッセンジャーのように、穏やかなβスイッチの方を好んで、そっと押す性質があるのです。その親和性は、αスイッチに比べて約20倍も高いという報告もあります。
この「βスイッチを選択的に押す」という賢い働きこそが、イソフラボンの恩恵の源泉です。
骨に多く存在するβスイッチが押されることで、骨の健康維持がサポートされ、脳や血管のβスイッチが優しく刺激されることで、ホットフラッシュや気分の落ち込みといった、あの独特のゆらぎが和らぐと考えられています。一方で、過剰な刺激は避けたいαスイッチへの影響は限定的であるため、ホルモン補充療法で懸念されるようなリスクが低いとされる科学的根拠も、ここにあります。
イソフラボンは、単にホルモンの代役を務めるのではなく、私たちの身体が持つシステムを理解し、必要な場所で、必要な分だけ、優しく応答してくれるパートナーのような存在なのです。
「あの人には効いて、私には…?」効果の個人差、その鍵は腸にありました
ここまで読んで、「でも、自分にはあまり効果を感じられなかった」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。その感覚は、決して気のせいではありません。なぜ同じように大豆製品を摂っていても、効果の現れ方に違いが出るのか。その最大の謎も、近年の研究で解き明かされつつあります。
答えは、私たちの「腸内」にいました。
大豆イソフラボンが体内に吸収される際、腸内にいる特定の細菌の働きによって、「エクオール」という、より活性の高い物質に変換されることがあります。このエクオールこそが、イソフラボンの恩恵を最大限に引き出す立役者だったのです。
そして、このエクオールを体内でつくり出せる能力は、すべての人に備わっているわけではありません。腸内にエクオール産生菌がいるかどうかによって決まるため、「エクオール産生者」と「非産生者」に分かれるのです。
この産生能力の有無が、効果の個人差を生む大きな要因でした。特にホットフラッシュの緩和効果においては、エクオールをつくれるかどうかで、その体感が大きく変わることが多くの研究で示されています。
興味深いことに、伝統的に大豆を食してきたアジア人では約50-60%がエクオール産生者であるのに対し、欧米人ではその割合が約25-35%に留まるというデータもあります。古くからの食生活が、私たちの身体の応答の仕方を育んできたのかもしれませんね。
もし、これまであまり効果を実感できなかったとしても、それはあなたの身体が悪いわけでは決してなく、ただ、腸内のパートナーとの出会いがまだなかっただけ、と考えることができるのです。
身体との対話を、今日から。内なるパートナーを育む暮らし
では、この賢いメッセンジャーの働きを、私たちの暮らしの中で最大限に活かすにはどうすれば良いのでしょうか。そのヒントは、やはり日々の食生活の中にありました。
大切なのは、「エクオール産生菌」という内なるパートナーが、元気に働けるような環境を整えてあげることです。
彼らの何よりのご馳走は、「食物繊維」や「プレバイオティクス」です。特に、玉ねぎ、ニンニク、ニラなどに含まれる「イヌリン」という水溶性食物繊維は、エクオール産生を助ける善玉菌を育むことが研究で示されています。
大豆製品を食事に取り入れるだけでなく、こうした野菜を一緒に摂ることを意識してみる。それは、単に栄養素を摂取するという行為を超えて、自分の中にいる小さな生き物たちを育み、身体の応答力を高めていく、という holistic(包括的)なアプローチです。
「減っていくこと」に不安を感じるのではなく、「今ある身体と、どう賢く付き合っていくか」へ。
その視点の転換が、ゆらぎの季節をしなやかに乗りこなす、一番の力になってくれるのかもしれません。
あなたの身体は、あなたが思う以上に、繊細で賢い応答システムを備えています。
今日の食事が、未来のあなたへの、優しいエールとなりますように。
(この投稿は、以下の科学的知見を参考にしています。)
論文1: Hooper, L., Ryder, J. J., Kurzer, M. S., Lampe, J. W., Messina, M. J., Phipps, W. R., & Cassidy, A. (2024). "Effect of Soy Isoflavones on Measures of Estrogenicity: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials". The Journal of Nutrition, 154(3), 819–832.
解説: 40件の質の高い研究を統合解析し、大豆イソフラボンの摂取が体内の主要な女性ホルモン(エストラジオール)や卵巣機能を示すホルモン(FSH)のレベルに影響を与えないことを高い確実性をもって結論付けた、非常に信頼性の高い研究です。イソフラボンの作用がホルモン量を「増やす」ものではないことの強力な根拠となります。
論文2: Wang, Y., Lyu, H., Zhang, J., Wu, L., Yang, S., & Wu, H. (2024). "Effects of soy isoflavones on menopausal symptoms in perimenopausal women: a systematic review and meta-analysis". PeerJ, 12, e19715.
解説: 12件の研究を統合し、大豆イソフラボンがホットフラッシュなどの血管運動神経症状、頭痛、気分の変動といった精神社会症状、動悸を含む更年期症状全体を、統計的に意味のあるレベルで改善することを示した最新のメタアナリシスです。
論文3: Baranska, A., Kanadys, W., Bogdan, M., & Stelmach-Mardas, M. (2022). "The Role of Soy Isoflavones in the Prevention of Bone Loss in Postmenopausal Women: A Systematic Review with Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials". Journal of Clinical Medicine, 11(13), 3863.
解説: 18件のランダム化比較試験を分析し、イソフラボンの摂取が閉経後の女性の腰椎および大腿骨頸部の骨密度を顕著に増加させることを示したメタアナリシスです。イソフラボンの骨に対する保護効果の強力なエビデンスとされています。
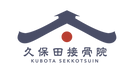



コメント